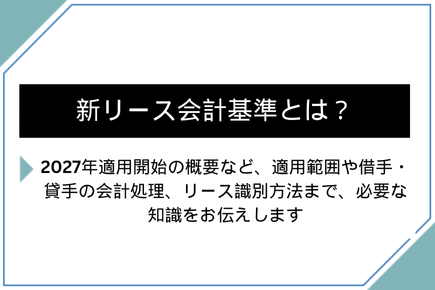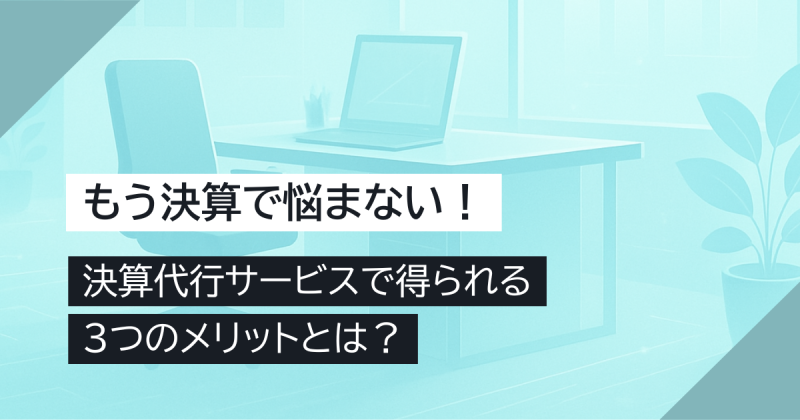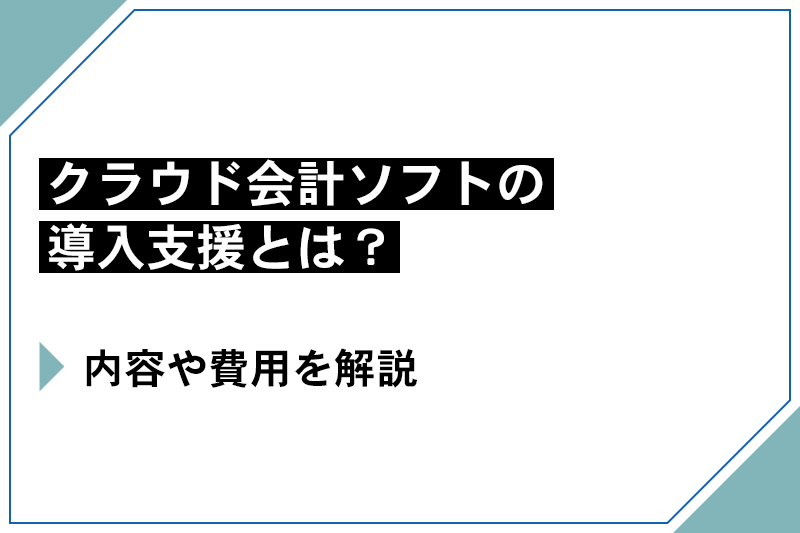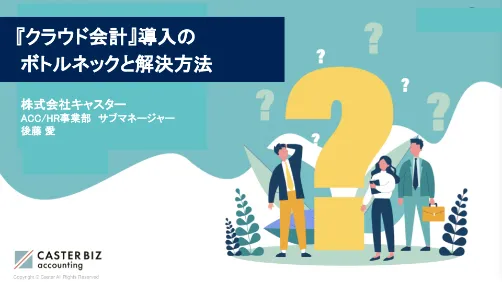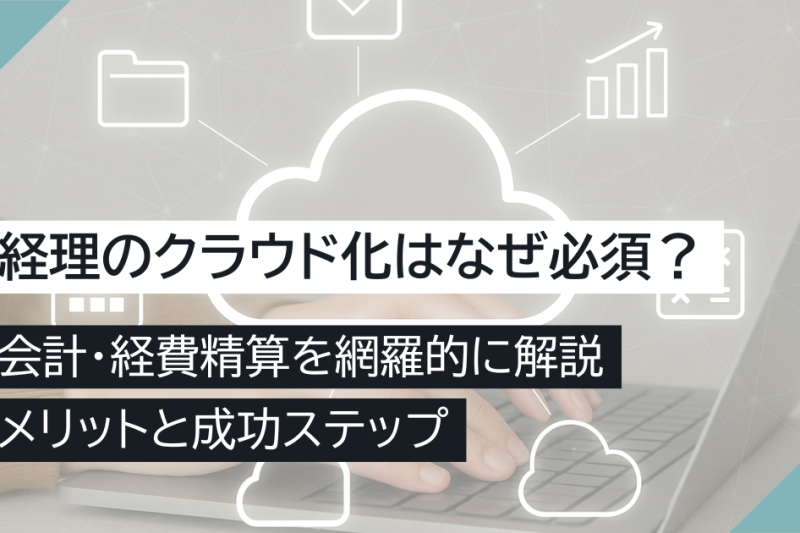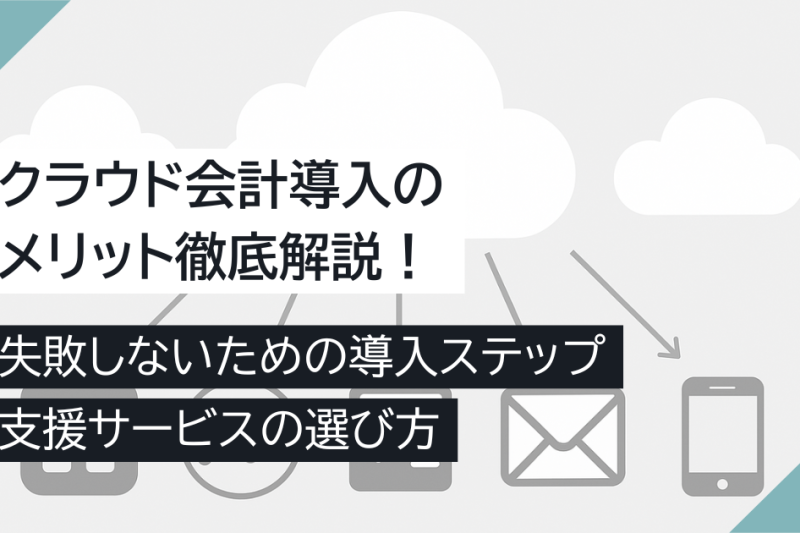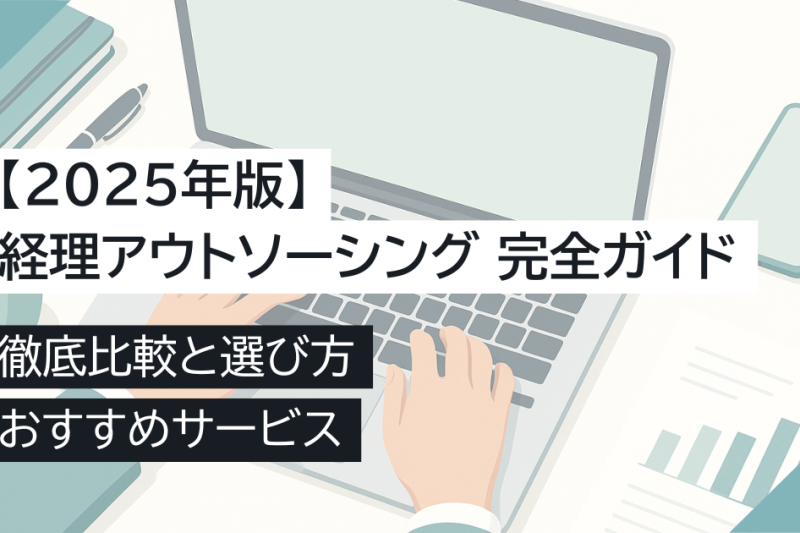電子帳簿保存法の「期限」とは?2024年完全義務化への対応ポイントを解説
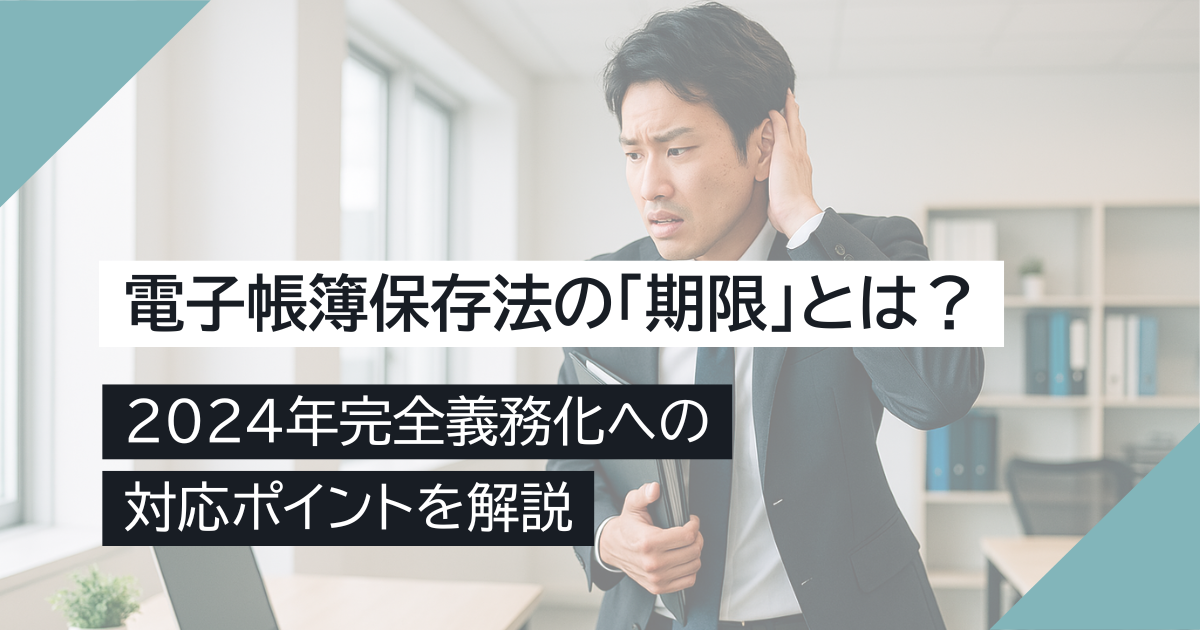
電子化の流れとともに、経理業務の在り方を大きく変えた「電子帳簿保存法(電帳法)」。
特に2024年1月1日から完全義務化された「電子取引データの保存対応」は、すべての企業にとって待ったなしの状況です。
「猶予期間が終わったって聞いたけど、結局いつまでに何をすればいいの?」「対応が間に合っていないけど大丈夫?」と不安を抱える経理担当者も少なくありません。
本記事では、電子帳簿保存法における「期限」の基本をわかりやすく整理し、対応を怠ることで生じるリスクや、実務対応の難しさを具体的に解説します。
電子帳簿保存法の「期限」とは? 混乱しやすい3つの期間を解説
そもそも電子帳簿保存法って何? 目的と対象書類
電子帳簿保存法(電帳法)は、経理書類を電子的に保存することを認める法律で、ペーパーレス化・業務効率化・コンプライアンス強化を目的としています。
対象となるのは以下の3カテゴリです。
- 帳簿:仕訳帳、総勘定元帳など
- 書類:請求書、領収書、見積書など
- 電子取引データ:メールやウェブで受け取るPDF請求書など
このうち最も注目すべきは、「電子取引データ」です。
2024年1月以降は電子取引データを電子で保存することが義務となり、紙に印刷して保存するだけでは法令上の保存要件を満たしません。
宥恕期間は終了しましたが、『相当の理由』がある場合には一時的な救済措置(紙での提示等)が認められることがあります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合、保存時に求められる要件(検索機能や改ざん防止など)を満たしていなくても違反にはなりません。
- 要件を満たす電子取引データの保存が困難である場合(申請不要)
- 税務調査などの際に、電子取引データのダウンロードの求めおよび印刷書面の提示・提出に応じられる場合
ただし、印刷書面のみを保存して電子データを削除する対応は認められません。
電子データの検索要件や改ざん防止措置を取らない場合でも、電子データ自体を適切に保存しておくことが義務とされています。
また、検索要件を不要とする措置の対象も拡大されています。
基準期間(法人なら2事業年度前、個人なら前々年)の売上が5,000万円以下の事業者は、税務職員の求めに応じてデータをダウンロード提供できる体制があれば、検索要件を備えなくてもよいとされています。
さらに電子取引データを取引年月日や取引先ごとに整理して紙で提示・提出できる体制がある場合も対象に含まれます。
つまり、あくまで原則は電子保存義務ですが、中小企業などに対しては一定の柔軟性が認められ、段階的に対応を進められるよう配慮されています。
2つの重要な期限:「保存期間」
帳簿や書類の保存期間は、法人で原則7年間(最長10年)、個人事業主では原則5年(最長7年)です。
これは必須の期限で、税務調査などで提示を求められる場合もあります。
(補足)宥恕期間(ゆうじょきかん)
2022年の改正で導入された「電子取引データ保存義務」には、当初2年間の宥恕期間(猶予期間)が設けられていました。
その期間は2023年12月31日までで終了し、2024年1月1日からはすべての企業が電子保存対応を行なう必要があります。
最重要! 2024年1月1日から完全義務化された「電子取引」の対応期限
期限を過ぎたらどうなる? 罰則・リスクの解説
電子取引データを適切に保存していない場合、青色申告の承認取消や追徴課税の対象となるリスクがあります。
さらに、法令違反が発覚した際には企業の信頼低下にもつながりかねません。
これは電子帳簿保存法だけでなく、法人税法や消費税法など他法令との整合性にも関係するため、単なる記録ミスでは済まない問題です。
猶予措置の終了と、今後の対応
2024年以降は、すべての電子取引データ(メール添付の請求書、ウェブ発行の領収書など)を電子的に保存することが義務化されています。
保存には以下の2点が求められます。
- 真実性の確保:改ざん防止(タイムスタンプ、事務処理規定など)
- 可視性の確保:検索機能や整然とした保存体制
【チェックリスト】自社の対応状況を確認しよう
- 電子請求書や領収書を紙で印刷して保存していないか?
- タイムスタンプや電子署名による改ざん防止を行なっているか?
- 電子データを検索・抽出できる環境を整備しているか?
- 電子保存に関する社内規定(事務処理規定)を策定しているか?
1つでも「いいえ」があれば、電帳法対応が不十分な可能性があります。
期限に間に合わない・対応が大変な企業が増加中! その3つの理由とは?
業務フローの変更やルールの策定に時間がかかる
電子帳簿保存法への対応は、単なるシステム導入ではなく、全社的な業務フローの見直しが必要です。
特に、電子取引データの処理ルールを明文化した「事務処理規定」の策定と運用には、多くの時間とリソースを要します。
経理担当者の業務外の負担となり、人的リソースが不足する
経理担当者は日常業務に加え、法改正対応や新システムの導入・教育も担うことになり、負担が増加しています。
専門知識を必要とするうえ、他部署との連携も必要なため、限られたリソースでは十分に対応できないケースが多く見られます。
専門知識の習得やシステム導入のコストがかかる
電子帳簿保存法は頻繁に更新されるため、最新の法令知識を維持するだけでも負担です。
また、文書管理システムやクラウド会計ツールの導入・運用コストも中小企業にとっては重い出費となります。
期限対応と日々の負担を軽減! 経理代行を利用する3つのメリット
メリット1: 専門家による確実な法対応で「期限」の不安解消
経理代行サービスには、電子帳簿保存法に精通した専門スタッフが在籍。
法令に則った運用設計・規定策定を支援し、期限を守るための正しい対応を安心して任せられます。
メリット2: 業務フロー構築から代行するため、経理担当者の負担がゼロに
電子取引データの受領から保存・検索までのプロセスを丸ごと代行。
社内工数を最小限にし、経理担当者は経営分析や戦略立案といったコア業務に集中できます。
メリット3: 採用や教育コストをかけずにスピーディーに対応可能に
専門知識を持つ外部スタッフを即戦力として活用できるため、採用・教育の手間なく短期間で法対応を完了できます。
電子帳簿保存法の確実な対応もサポート! キャスターの経理代行が選ばれる理由
キャスターの経理代行なら電子帳簿保存法に対応した業務設計も代行
CASTER BIZ accountingは、記帳代行にとどまらず、電子帳簿保存法に準拠した経理業務設計をトータルで支援します。
お客様の現状やシステム環境に合わせて最適な保存フローを設計し、法対応をスムーズに進められる仕組みを構築します。
経験豊富なプロフェッショナルが御社の状況に合わせて柔軟に対応
公認会計士・税理士資格者を含む経験豊富なチームが、業種・規模・システムに合わせて柔軟に対応。
「自社の規模でもお願いできる?」という不安にも丁寧に応え、実務に即したサポートを提供します。
まとめ
電子帳簿保存法の完全義務化により、企業はもはや対応を先延ばしにできません。
期限を守ることはもちろん、これを機に経理のデジタル化と効率化を進める絶好のタイミングです。
自社だけでの対応が難しい場合は、CASTER BIZ accounting(株式会社キャスター)の活用を検討してみてください。
専門チームがシステム導入による法対応から運用設計までを包括的にサポートし、安心・確実な経理体制を実現します。