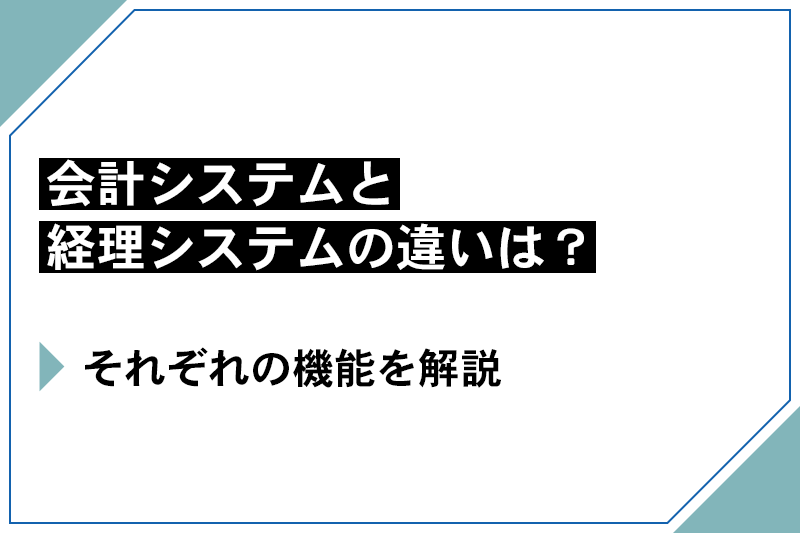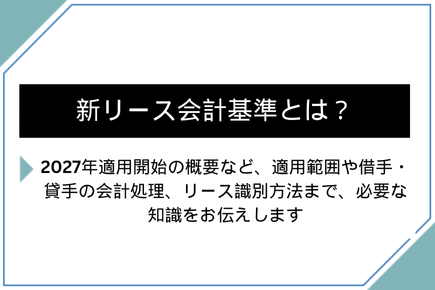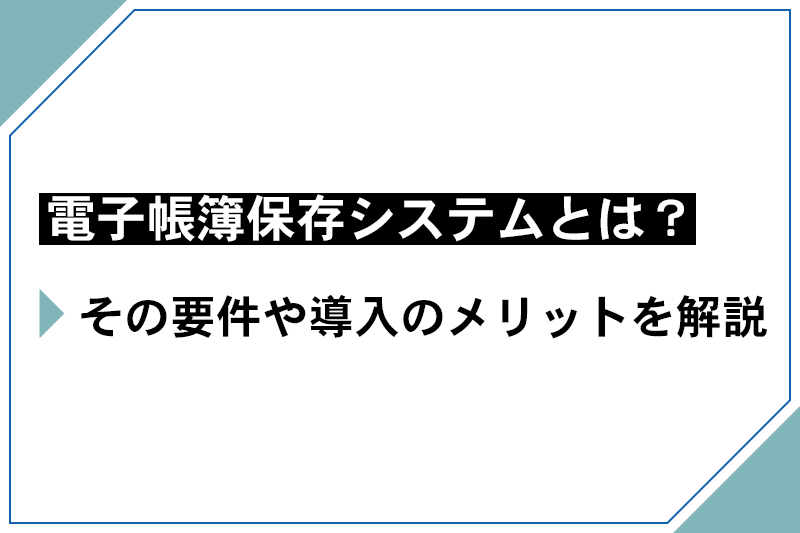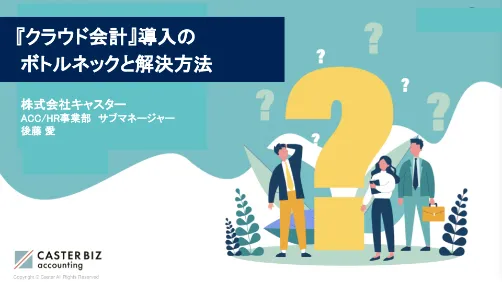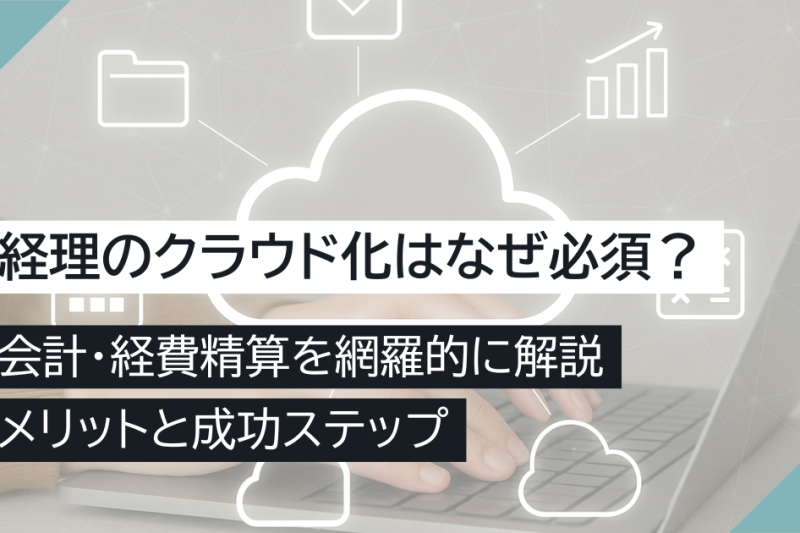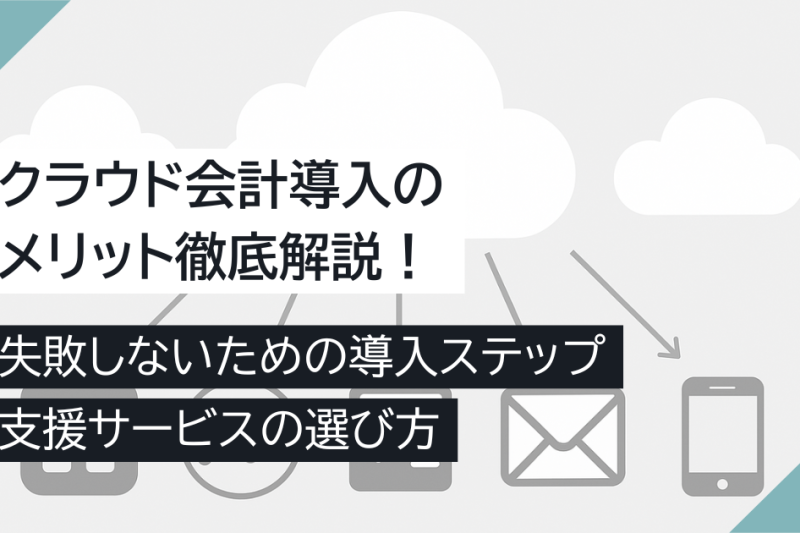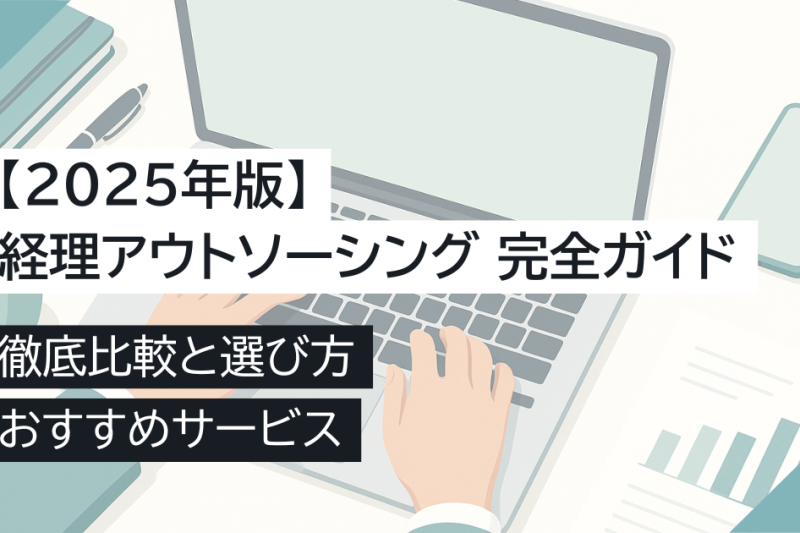電子帳簿保存法で紙の領収書はどうする?保存や廃棄方法の解説も
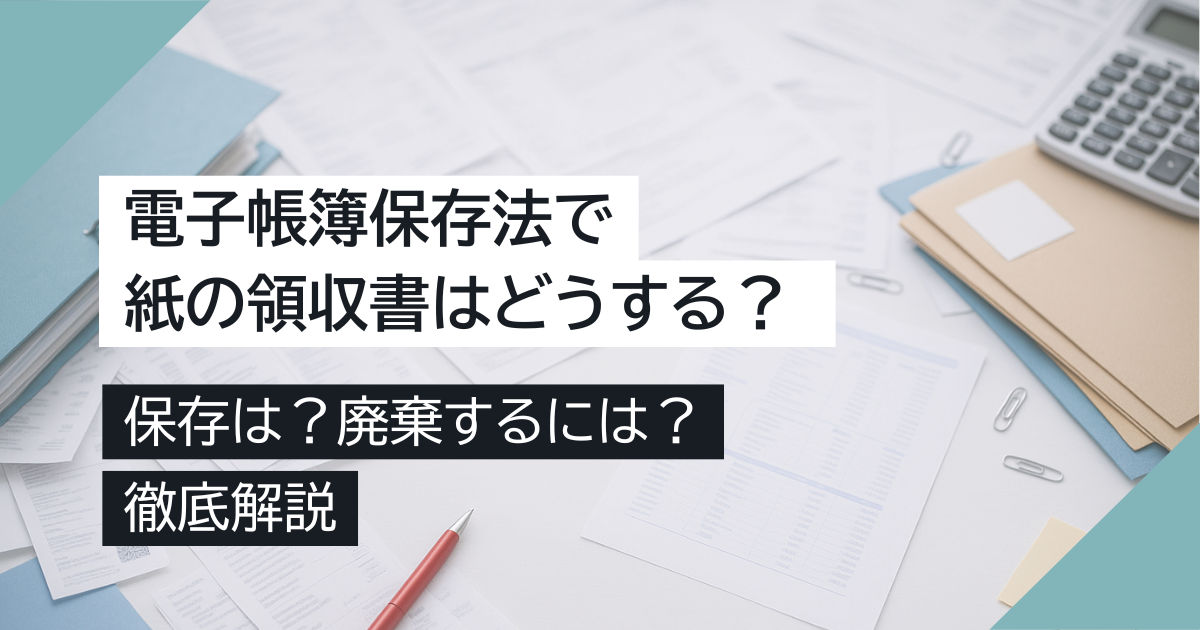
電子帳簿保存法の施行により、経理業務のデジタル化は避けて通れないテーマとなりました。
そのなかで特に多い疑問が、「日々発生する紙の領収書をどう扱えばよいのか?」というものです。
電子取引のデータ保存義務が話題になる一方で、実務では今なお紙の領収書が一定数発生しています。
これらをどのように扱い、どこまで電子化できるのか、そして紙を破棄しても問題ないのか――。
本記事では、電子帳簿保存法における紙の領収書の位置づけから、スキャナ保存の要件・具体的な手順・破棄の可否までを詳細に解説します。
さらに、これらの対応に伴って増大する業務負荷を軽減する方法として、経理代行の活用を提案します。
電子帳簿保存法の基礎知識|紙の領収書が関連する保存区分
電子帳簿保存法とは?(対象となる文書と目的の解説)
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係帳簿書類の電子的な保存を認める法律です。
従来は紙での保存が原則でしたが、電子データとしての保存を可能にすることで、企業のデジタル化を推進する狙いがあります。
対象となる文書は大きく3つに分けられます。
| 保存区分 | 対象書類 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで作成した帳簿・決算書類 | 総勘定元帳・仕訳帳など |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書・請求書などを電子化して保存 | 領収書・契約書・見積書など |
| 電子取引データ保存 | メール・クラウド・EDIなどで授受した電子データ | PDF請求書・クラウド経費データなど |
紙の領収書はこのうち「スキャナ保存」に該当します。
つまり、電子帳簿保存法では「紙をスキャンして電子化した画像」を正式な保存データとして認める制度設計になっています。
この法律の目的は、税務調査においても正確性・真正性が確保されたデータを迅速に提示できる環境を整えることです。
単に紙をデータ化するだけでなく、改ざん防止や検索性の確保など、税務実務に耐えうる形で保存することが求められます。
紙の領収書は「スキャナ保存」の対象となり得る
紙で受領した領収書や請求書、契約書などは、電子帳簿保存法上の「国税関係書類(重要書類)」にあたります。
これらを電子的に保存するには、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。
2022年1月の法改正によって、税務署長の事前承認が不要になり、さらに「適正事務処理要件(相互牽制・定期検査など)」が廃止されたことで、実務負担は大幅に軽減されました。
これにより、企業の判断でスキャナ保存を導入できるようになり、中小企業でも対応が進めやすくなっています。
「紙の領収書はどうする?」具体的な電子保存の手順と要件
スキャナ保存の「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を徹底解説
電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存では、以下の2つの要件が柱となります。
1. 真実性の確保
スキャンした画像データが改ざんされていないことを証明するための要件です。
主に次のいずれかの方法で対応します。
- タイムスタンプを付与:スキャン後に日付付きの電子署名(タイムスタンプ)を付与することで、データの真正性を証明。
- 訂正・削除履歴が残るシステムで保存:クラウド会計ソフトや文書管理システムなど、変更履歴を自動で記録できるツールを使用することで代替可能。
これにより、「後から改ざんしていない」ことが税務上も確認できます。
2. 可視性の確保
保存したデータをすぐに確認できる状態に保ち、取引年月日・金額・取引先名で検索できるようにしておくことが必要です。
さらに、画面表示や印刷によって帳票の内容を整然と確認できる形式であることが求められます。
これにより、税務調査の際にも紙の帳票と同等の精度でデータを確認できるようになります。
これらを満たすことによって、紙の領収書を「電子帳簿保存法に準拠した正式な証憑」として扱うことが可能になります。
領収書の受領から紙を破棄するまでの具体的な流れ
電子帳簿保存法のスキャナ保存を正しく運用するためには、以下のようなステップを踏む必要があります。
① 領収書の受領
取引先や店舗から受け取った紙の領収書を、受領者(社員)が保管します。
② スキャンまたは撮影
受領からできるだけ早く、スキャナやスマートフォンなどで画像データ化します。
このとき、受領者本人がスキャンするか、もしくは受領者と同一部署の別担当者が行なう必要があります。
③ タイムスタンプの付与
スキャン後、おおむね2カ月以内(最長約2カ月+概ね7営業日以内)にタイムスタンプを付与するか、訂正履歴が残るシステムにアップロードします。これが真実性確保の鍵となります。
④ データ入力・検索項目の設定
画像データに「取引年月日」「金額」「取引先名」などの検索キーを紐付けます。これは会計ソフトや経費精算システムの自動連携機能を利用すると効率的です。
⑤ 紙の破棄
上記の要件をすべて満たした後、紙の領収書は原則として破棄可能です。ただし、スキャン前や要件未達成の状態で破棄してしまうと、税務上の証憑として認められないリスクがあります。
この流れを正確に行えば、「紙の領収書はどうするべきか」という疑問に対して、「要件を満たして電子化した後は、安心して破棄できる」と明確に答えられます。
スマホ撮影や自炊(PDF化)は認められる?
結論から言えば、スマートフォンや複合機を使ったPDF化でも、電子帳簿保存法上のスキャナ保存として認められます。
ただし、次の技術要件を満たす必要があります。
- 解像度200dpi以上でスキャン
- カラー画像(赤・青・緑の階調を持つ)で保存
- データ改ざん防止措置(タイムスタンプまたは履歴管理)を講じる
- ファイル名やメタデータで検索項目を設定できる
これらを確実に満たすには、専用の経費精算システムや文書管理システムの導入が最も安全です。
例えば、クラウド型の経費精算ツールでは、スマホ撮影後に自動でタイムスタンプを付与し、検索項目を生成する仕組みを備えています。
手作業での処理ミスや要件漏れを防ぐためにも、システム運用が推奨されます。
電子帳簿保存法対応の「業務負荷」と「経理代行」という選択肢
法対応を自社で行う場合に発生する業務負荷
スキャナ保存の仕組みを自社で導入・運用する場合、想像以上に多くの工数が発生します。
社員教育・マニュアル整備
電子帳簿保存法のルールを全社員に理解させるための研修や運用ルール作成が必要。ルール徹底の難易度が高く、抜け漏れが発生しやすい。
スキャン・データ入力の作業工数
領収書を受領するたびにスキャン、タイムスタンプ付与、データ登録を行う手間が増大。繁忙期には処理が滞ることも。
チェック体制・監査対応
内部監査や定期的な検証を行う体制を維持しなければならず、管理者の負担が大きい。
紙の一時保管と廃棄管理
スキャナ保存完了までの一時保管や、破棄時期・方法の管理も必要。紙の保管コストや紛失リスクも無視できません。
このように、スキャナ保存を正しく運用するためには、法的知識・業務設計・IT環境の3要素を同時に整える必要があり、多くの企業が「人手も時間も足りない」という壁に直面します。
経理代行を利用することで法対応の課題を解消
こうした課題を根本的に解決できるのが、経理代行サービスの活用です。
経理代行では、電子帳簿保存法の要件を踏まえたスキャナ保存の運用を、専門チームが代行します。
法令遵守の安心感
最新の電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した運用設計を行い、企業が不安なく法対応できる体制を整備。
業務標準化と自動化の推進
領収書回収からスキャン、データ化、会計連携までのフローをシステムで標準化。属人化を防ぎ、担当者が変わっても安定運用が可能。
コア業務への集中
経理担当者が単純作業から解放され、経営分析や改善提案など、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。
電子帳簿保存法に対応し、業務を効率化するならキャスターの経理代行
理由1: 法改正を熟知したプロが対応
CASTER BIZ accounting は、電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新法令を熟知した専門チームが担当。
税務・会計実務に基づいた正確な運用設計で、貴社の電子帳簿保存体制を安心して構築できます。
理由2: 業務の完全デジタル化を支援
領収書の回収・スキャン・データ化・クラウド保存を一気通貫で代行します。
電子帳簿保存法対応だけでなく、経費精算や仕訳処理までをシームレスに連携することで、紙の処理を最小限にし、バックオフィス全体の生産性を向上させます。
理由3: 貴社に合わせた柔軟な運用体制
クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生会計など)との連携や、既存システムの活用にも柔軟に対応。
企業規模や業種に合わせて、最適な運用フローを設計します。
まとめ(再確認と行動促進)
電子帳簿保存法は、単なる「法令遵守の義務」ではなく、企業が経理業務を効率化する大きなチャンスです。
紙の領収書もスキャナ保存の要件を満たせば、法的に問題なく電子化・破棄が可能。これにより、保管スペースや管理コストを削減し、経理部門の生産性を大幅に向上させることができます。
しかし、法対応を自社だけで完璧に運用するのは簡単ではありません。
もし「電子保存のルールを整備する余裕がない」「人手が足りない」と感じている場合は、CASTER BIZ accounting の経理代行サービスをご検討ください。
法改正を熟知した専門チームが、電子帳簿保存法対応から業務設計までを包括的にサポートします。
経理業務のデジタル化を推進し、安心して法令遵守を実現する第一歩を、いま踏み出しましょう。