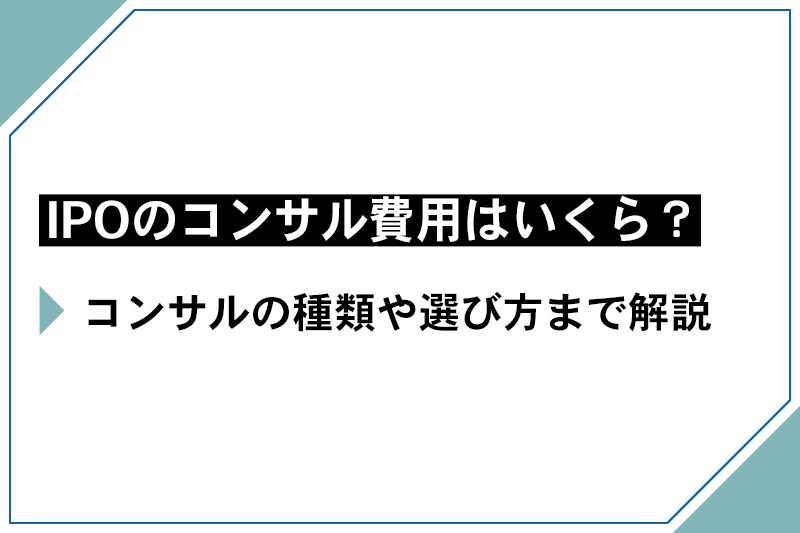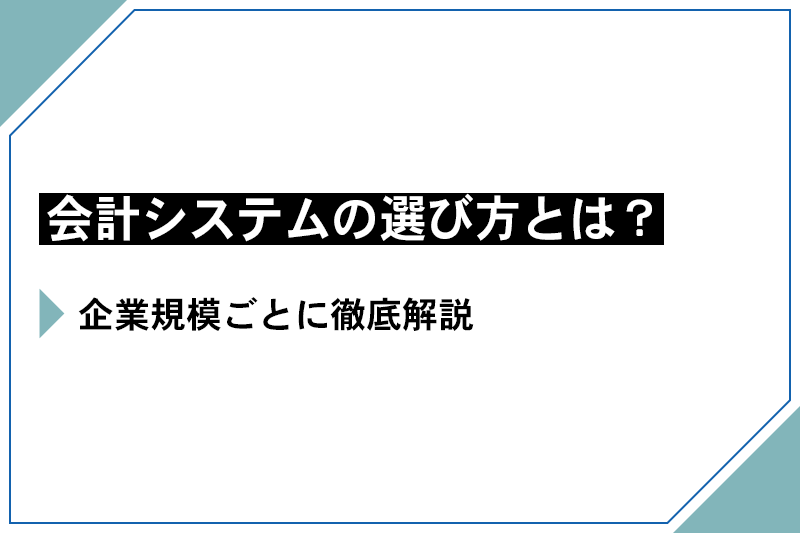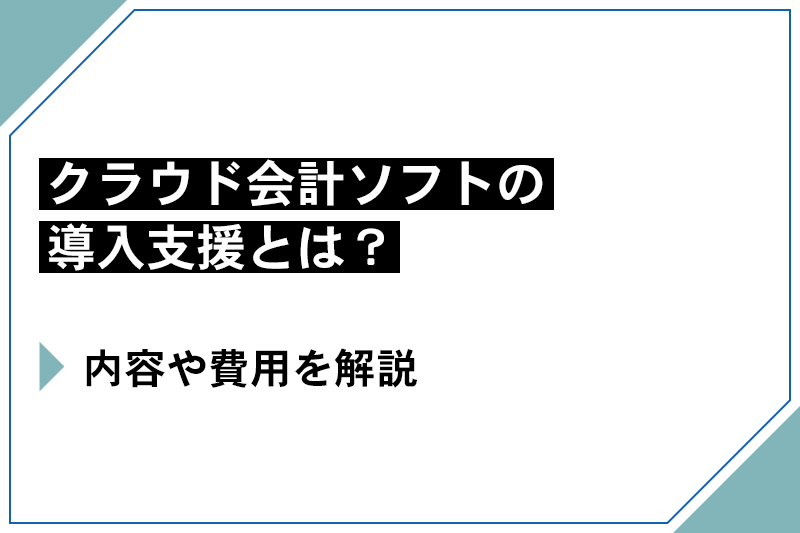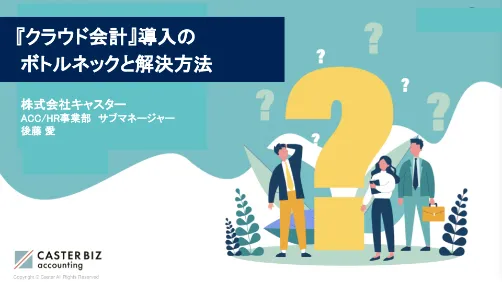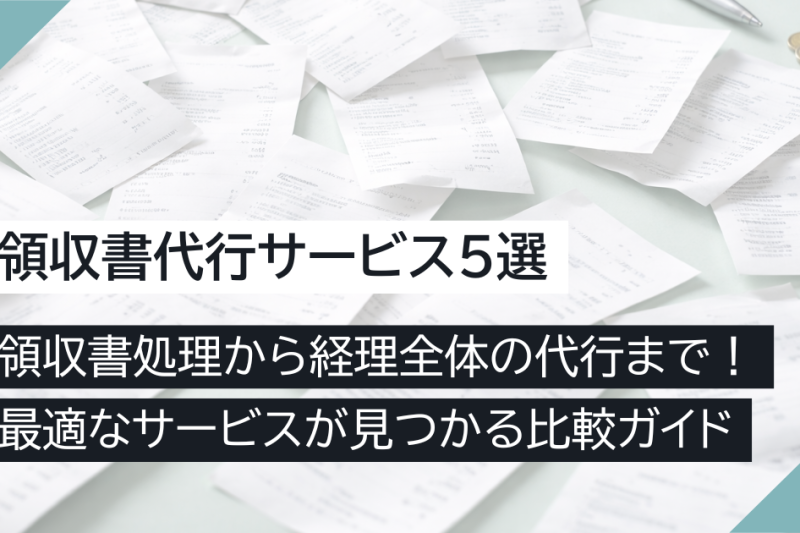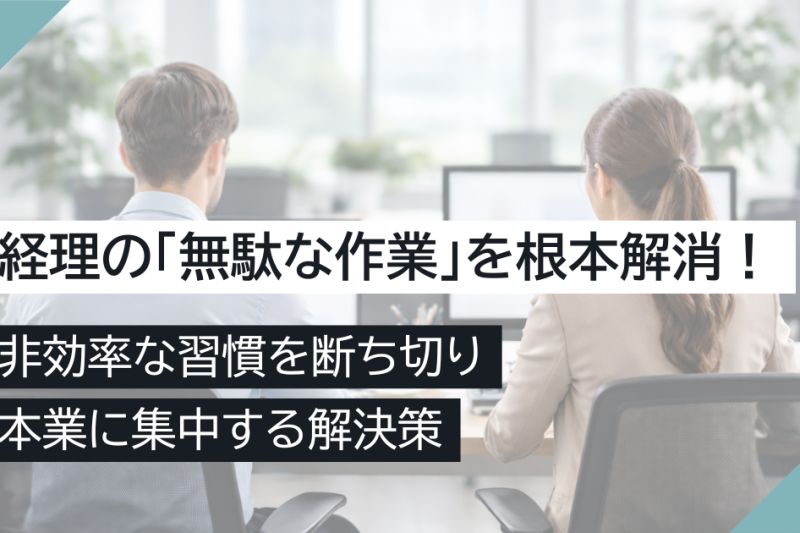税理士費用が高いと感じたら?すぐに取るべき行動3選
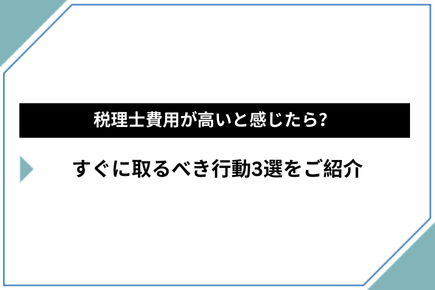
「税理士費用が高い気がする……」「安くしたいけど、具体的に何をしたらよいのかが分からないと、お悩みではありませんか?
もし見直すのなら、税理士費用をなるべく抑えつつ、依頼を効率化したいですよね。
そこで本記事では、税理士費用の相場をお伝えしたのちに、税理士費用を抑えるためにとるべき3つの行動をご紹介します。
すぐにでも税理士費用を安くしたい企業様は、ぜひ最後までご覧ください。
税理士費用に差が生まれる要因

【税理士費用に差が出る要因】
- 売上規模
- 従業員数
- 面談の頻度
税理士費用の違いは、なぜ生じるのでしょうか。
ここでは、税理士費用に差が出る正当な理由を3つご紹介します。
売上規模
依頼者の会社の売上規模は、税理士費用を左右する要因の一つです。
売上規模が大きくて取引先の多い会社では、帳簿作成や決算申告などの業務が複雑になるため、税理士の負担も増加します。
また、そのような会社は支払う税金の額も高いので、税理士には節税の高度な知識が求められます。
このように、売上規模に応じて税理士の業務量や求められる知識量が変わるため、費用にも差が生じるというわけです。
従業員数
従業員数が多い会社も、税理士費用が高くなる傾向にあります。
その理由は前項と同じく、税理士に求められる業務量や知識量が多くなるからです。
税理士事務所では顧問料のほかに、従業員数に応じて実費を上乗せするケースも珍しくありません。
面談の頻度
面談を頻繁に行っている場合も、税理士費用は高くなります。
税理士は、会社の直近の経営状況や財務状況を詳しく把握するために、定期的に面談を行います。
その頻度は依頼内容によって異なりますが、多ければ月に1回ほどのペースで実施されることもあるでしょう。
面談の頻度が高いほど税理士の負担も増えるので、それだけ税理士費用も高額になってしまいます。
税理士費用の相場
続いて各種税理士費用の相場を、事業形態別にお伝えします。
なお以下の2つの表はいずれも、年に1回税理士との面談を行っている場合の費用の相場です。
法人
法人の税理士費用の相場
| 売上規模 | 顧問相場(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
| ~1,000万円 | 15,000円 | 7,000円 | 107,000円 |
| 1,000万~3,000万円 | 19,000円 | 8,000円 | 129,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 23,000円 | 11,000円 | 150,000円 |
| 5,000万~1億円 | 29,000円 | 14,000円 | 173,000円 |
| 1億~5億円 | 40,000円 | 20,000円 | 210,000円 |
| 5億~10億円 | 50,000円 | 26,000円 | 235,000円 |
(いずれも税込)
法人の場合、税理士費用のベースとなる顧問料と、基本的な依頼内容である記帳・申告代行の相場は上記の通りです。
ただしこれらはあくまでも目安であり、実際にかかる税理士費用は、税理士や依頼者によって異なる点にご留意ください。
たとえば合同会社と株式会社で比較した申告代行の費用は、法人という括りは同じでも、あまり手間のかからない前者のほうが安い傾向にあります。
また、業種によっても税理士費用は異なります。
小売業や飲食業など、勘定科目が多い業種に比べると、コンサル業や広告業の方が支払う税理士費用は安価で済むでしょう。
実際にかかる税理士費用は見積もりを取るまでわからないので、自社の依頼にいくらで対応してもらえるのか、まずは相談する必要があります。
個人事業主・フリーランス
個人事業主・フリーランスの税理士費用の相場
| 売上規模 | 顧問相場(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
| ~1,000万円 | 13,000円 | 6,000円 | 76,000円 |
| 1,000万~3,000万円 | 17,000円 | 7,000円 | 96,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 21,000円 | 10,000円 | 116,000円 |
| 5,000万~1億円 | 28,000円 | 13,000円 | 145,000円 |
(いずれも税込)
法人に比べて、個人事業主・フリーランスの税理士費用は安いといえます。
事業の規模が小さい分、税理士費用を左右する売上規模もそこまで大きくないため、比較的リーズナブルに利用できます。
しかし個人事業主・フリーランスの場合、税理士とそもそも契約せずに、ご自身で記帳や決算申告を行う方も多いようです。
法人ほど仕訳数が多くなく、税理士費用を支払ってまで代行を依頼するメリットがあまりないからです。
個人事業主・フリーランスに限った話ではありませんが、本当に税理士と契約する必要があるのか、いま一度考えてみてもよいかもしれません。
税理士費用が高いと感じたときに取るべき行動
【税理士費用が高いと感じたときに取るべき行動】
- 税理士費用の相場を確認する
- 依頼内容を見直す
- 無駄な依頼を省く
「税理士費用が高いかも……」と感じたら、上記3つのアクションを順番に起こしましょう。
①税理士費用の相場を確認する
まずは、現在支払っている税理士費用を相場と比較してください。
自社の売上規模や依頼内容に対して、請求額が過大ではないかを確認します。
もし相場よりも多額の税理士費用を支払っているなら、依頼内容を見直す余地があるかもしれません。
とはいえ、税理士費用の相場というのはなかなか確かめにくいものです。
先ほどご紹介した相場はあくまでも参考程度にとどめ、複数の税理士から相見積もりをとるのがおすすめです。
②依頼内容を見直す
次に、税理士と余計な契約を結んでいないかを確認します。
当然ですが、依頼の量が多ければ税理士の仕事量も増えるので、その分税理士費用は高くなってしまいます。
契約書に改めて目を通したり、依頼内容を書き出してみたりなど、依頼の内訳を正確に把握し、必要性を精査するところから始めるとよいでしょう。
③無駄な依頼を省く
依頼内容を確認し終えたら、そこから余計な契約を破棄します。
税理士費用を抑えるには、税理士との面談の頻度を減らす、外注していた年末調整を自社で行うようにするなど、最低限の依頼で済ませるための工夫が必要です。
ただし、必要以上に依頼を減らすと自社の税務負担が増えてしまうため、変更する依頼内容は、社内でよく話し合ってから決めましょう。
税理士を変更する際に考慮すべき点

【税理士を変更する際に考慮すべき点】
- レスポンスの早さ
- 料金システム
- 強みとしている業種
- 切り替えるタイミング
- 候補の選定時期
依頼内容を見直しても税理士費用が安くならない場合は、思い切って税理士を変えてみるのも一案です。
その際は、上記5つの点を考慮したいところです。
レスポンスの速さ
税理士を変更する際、さまざまな依頼に迅速に対応してくれるかどうかは、確かめておくべきポイントです。
会社の命運を分ける経営判断や、期日が決められている確定申告には、迅速な対応が求められます。
そんな大事な場面で税理士からのレスポンスが遅いと、判断や作業が遅れて、大きな損失を被ってしまうかもしれません。
レスポンスの良さを見分ける手段としては、契約前に面談の場が設けられるまでの期間や、見積もりを出すまでの早さを参考にする方法があります。
口コミや評判を見て判断するのもよいでしょう。
ただし、税理士の繁忙期である12月~3月にかけての期間は、どうしてもレスポンスに時間がかかりがちです。
この期間に税理士を変更する場合は、レスポンスが遅れる可能性がある旨を、正直に伝えてくれるところを選ぶのがおすすめです。
料金システム
その税理士事務所の料金システムがどうなっているのかも、税理士を変更するにあたって事前に確かめておきたい項目の一つです。
ひと口に“税理士費用”といっても、その内訳は多岐にわたります。
ベースとなる顧問料のほか、依頼する業務ごとに別料金がかかるケースがほとんどです。
そのため、「毎月の顧問料が安いから」という理由だけで税理士を選ぶと、業務を依頼するたびに出費がどんどんかさんでしまいます。
このような事態を防ぐためには、その事務所の料金システムや、同一料金で対応可能な業務の範囲をあらかじめ確認しておく必要があるのです。
強みとしている業種
決して安くない税理士費用を支払うからには、業務効率の改善や節税など、相応の効果を得たいものです。
費用対効果を最大化させるために、依頼する税理士がどのような業種のサポートを得意としているのかをリサーチしておきましょう。
税理士事務所の公式ホームページや口コミを見れば、強みとしている業種がわかるので、自社の業種がそれに該当しているか照らし合わせて見てください。
切り替えるタイミング
税理士を変更するなら、適切なタイミングを見計らうとよいでしょう。
多くの企業様に共通するベストな変更時期は、ずばり“年度の変わり目”です。
税理士を雇ってから決算日までの期間が長いので、会社の経理業務を覚える余裕が生まれ、確定申告をスムーズに行えるようになるからです。
また、年度の変わり目まで待てない場合は、税理士が余裕をもって引継ぎを行えるタイミングを見計らうのもよいかもしれません。
一般的に税理士の閑散期といわれている6月~11月のあいだであれば、時間をかけて詳細な引継ぎを行えるため、シームレスに新たな契約を始められます。
候補の選定時期
新しい税理士の候補は、今の契約を解除する前に選んでおくと安心です。
税理士に依頼する業務は、専門的な知識を要するうえに手間のかかるものがほとんどです。
新しい税理士の目星がつかないうちに今の契約を解除すると、経理担当者がその穴埋めに追われ、ほかの業務を圧迫してしまうおそれがあります。
これまでご紹介してきたポイントを参考に、新しい税理士の候補を決めておき、契約の空白期間が発生しないように図りましょう。
お悩みはございませんか? この業務は依頼できるのかな?
といったご質問等まずはご相談ください。
日常業務から会計システム導入まであらゆる経理業務をサポートする
オンライン経理のCASTER BIZ accountingです!

- 「サービス資料」をご提供いたします
- 貴社の業種業界に合わせた「導入事例」をご紹介いたします
- ご希望で「オンライン面談」をご予約いただけます
- 現状の「課題整理」をお手伝いいたします
- 導入後の「ご活用イメージ」をご提案いたします
税理士費用を安くする際に意識したいポイント

【税理士費用を安くする際に意識したいポイント】
- 面談の頻度や方式を最適化する
- 税理士費用だけでなくサービス内容も加味する
- 自社の人件費も考える
税理士を変更するときは、上記3つのポイントを意識することで、より大きな費用対効果を得られるようになります。
ポイント①面談の頻度や方式を最適化する
冒頭でもお伝えした通り、税理士費用は面談の頻度によって増減します。
「これまでに何度か面談してもらっているけど、いまいち効果を実感できていない」とお考えなら、頻度を見直してみる価値があります。
とはいえ、経営状況や財務状況に基づいたアドバイスをもらえる貴重な機会なので、むやみに減らせばよいというわけでもありません。
自社に適した面談の頻度がどれくらいなのか、よく見極めてから結論を出しましょう。
また面談の費用を削減するには、対面からオンラインに切り替えるというのも有効です。
なぜなら税理士費用のなかに、面談時の出張交通費が含まれている場合があるからです。
オンラインでの面談に対応しているかどうか、それによって税理士費用が減るのか、一度相談してみるとよいでしょう。
ポイント②税理士費用だけでなくサービス内容も加味する
サービス内容に着目して新たな税理士を選べば、見かけの数字以上の費用対効果を得られることもあります。
税理士費用を抑える最大の目的は、“手元に多くの利益を残すこと”ではないでしょうか。
たしかに、単純に費用を削減すればその目的は達することができます。
ただし同じ料金を支払うにしても、節税やコンサルティングにより精通した税理士を選べば、税理士費用は実質的に下がったも同然です。
依頼の効率を上げるためには、税理士費用の削減だけに固執せず、サービス内容も加味して税理士を選びたいところです。
ポイント③自社の人件費も考える
税理士費用を抑えるにあたっては、依頼をやめたあとに自社で発生する人件費も考えなければなりません。
たとえば記帳代行の依頼をやめる場合、自社で新たに経理担当者を用意する必要があります。
いくら税理士費用を抑えられたからといって、それ以上に人件費がかさんでしまっては、内製化した意味がありません。
目先の税理士費用だけでなく、トータルコストを抑えられるように意識しましょう。
税理士費用を抑えるリスク

【税理士費用を抑えるリスク】
- 対応してくれるサービスの範囲が変わる
- 節税効果が得られなくなる
- 自社の作業負担が増える
- 税理士の質が低下する
税理士を変えれば、費用の削減をはじめとするさまざまなメリットを享受できます。
一方で、上記のようなリスクが生じうることも想定しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
リスク①対応してくれるサービスの範囲が変わる
無理に税理士費用を抑えようとすると、十分なサービスを受けられなくなるリスクがあります。
税理士費用は、求めるサービスの範囲によって変動します。
そのため、費用が安い税理士と契約した場合に、今まで受けていたサービスが対応範囲外となってしまう可能性があるのです。
「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないためにも、税理士を変える際には、自社に必要なサービスを受けられるかどうかを必ず確認してください。
リスク②節税効果が得られなくなる
費用が安い税理士に依頼すると、節税効果が薄れてしまうリスクも考えられます。
前項で述べた対応範囲のほかに、サービスの品質も税理士費用によって上下します。
低価格で引き受けてくれたとしても、経験値の低い税理士であれば、節税に関する十分なアドバイスを得られなくなることもあるでしょう。
こういった事態を避けるには、想定している予算内で、その税理士が自社に十分な節税効果をもたらしてくれるかどうかを見極める必要があります。
事前の面談で話した内容や、公式ホームページに記載されている情報を参考にすれば、契約によって得られる効果をイメージしやすくなるはずです。
リスク③自社の作業負担が増える
経理担当者の負担が増える可能性がある点も、税理士費用を抑えるにあたって理解しておく必要があります。
繰り返しにはなりますが、税理士に依頼する業務は、専門的な知識を要するうえに手間のかかるものばかりです。
税理士費用の削減に伴って一部の業務を内製化すれば、経理担当者の負担が増加するわけですから、予期せぬミスが生じるリスクも高まるでしょう。
一部の業務を税理士に対応してもらえなくなった際に、社内のリソースだけで内製化が可能なのかを、事前によく詰めておかなければなりません。
リスク④税理士の質が低下する
費用が安い税理士に変える場合、サービスの品質だけでなく、税理士自体の質も下がってしまう可能性があります。
たとえばミスが多かったり、アドバイスが適切でなかったりする税理士は、質が低いといえます。
必ずしも「費用が安いと税理士の質も低い」とは限りませんが、そのような傾向があるのもまた事実です。
リーズナブルに依頼できる税理士をお探しであれば、事前に口コミを確認し、少しでも評判のよい税理士を選ぶようにしましょう。
税理士費用は、依頼内容の見直しや税理士の変更によって抑えることができる

今回は、税理士費用を抑えるためにとるべき3つの行動を、その際に意識したいポイントとともにお伝えしました。
依頼内容を見直して余計な契約を破棄することで、税理士費用は抑えられます。
ただしそれでも費用が高いと感じたら、税理士を変えてしまうのも一つの手です。
その際、面談の頻度や方式、サービスの質をなるべく落とすことなく移行できれば、より大きな費用対効果を得られるでしょう。
依頼内容の見直しを検討の企業様は、リモート経理チームのオンライン経理のCASTER BIZ accountingにお任せください。
依頼内容に応じて貴社専用のプランをご用意し、さまざまな経理業務を無駄なくサポートさせていただきます。