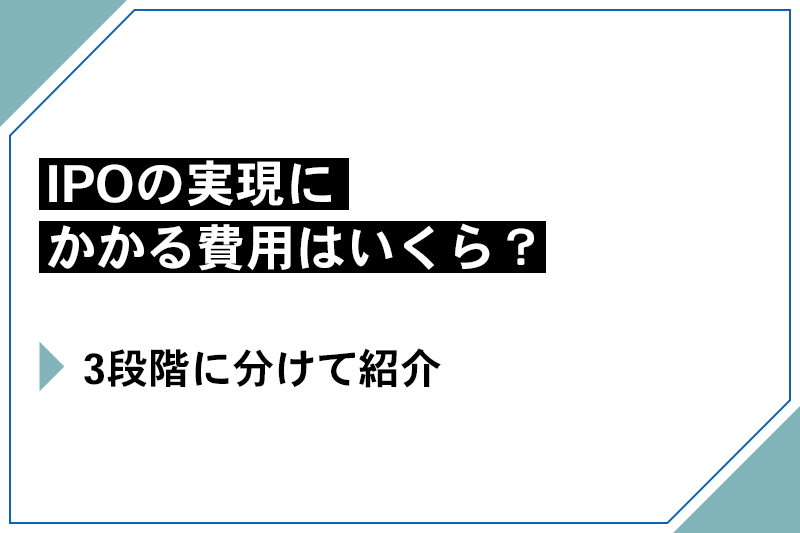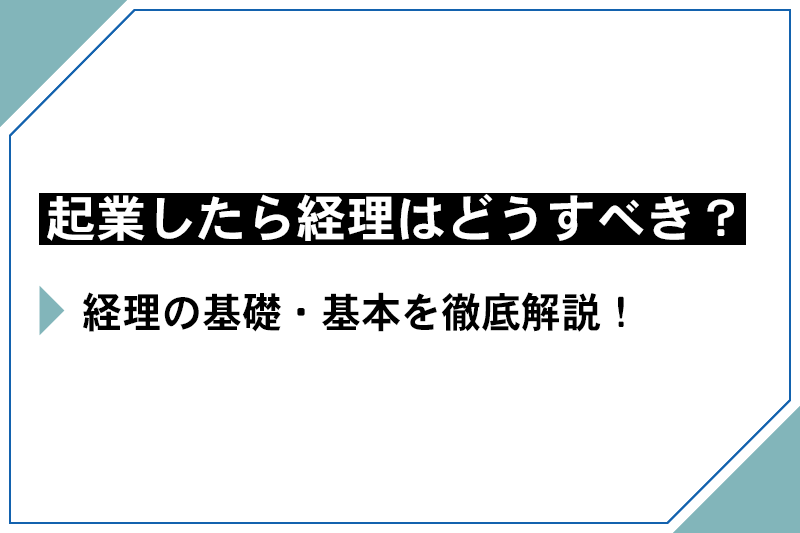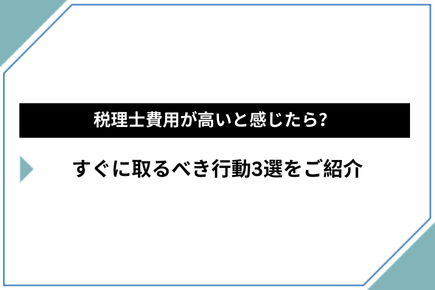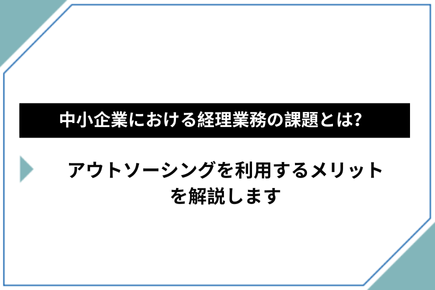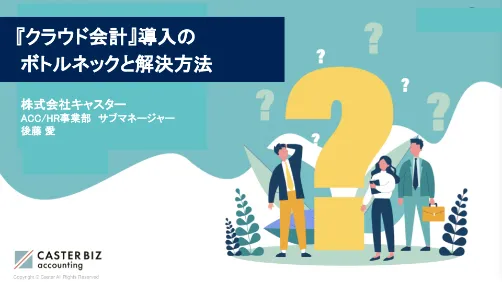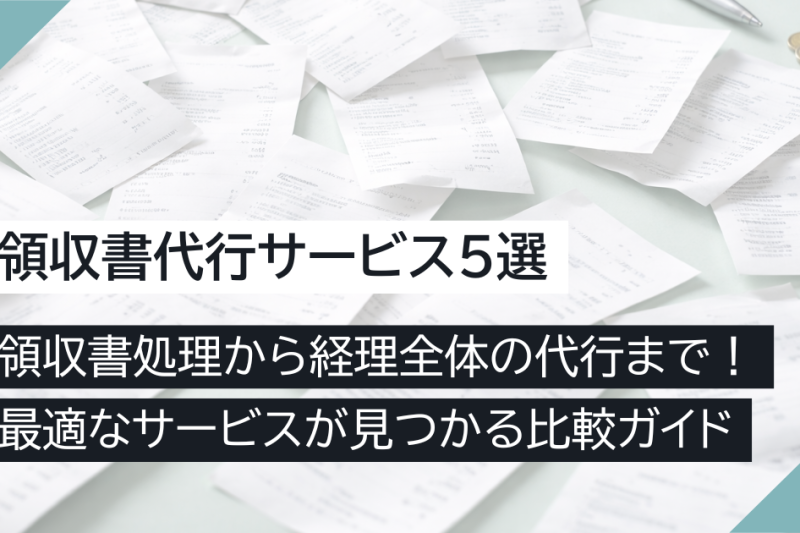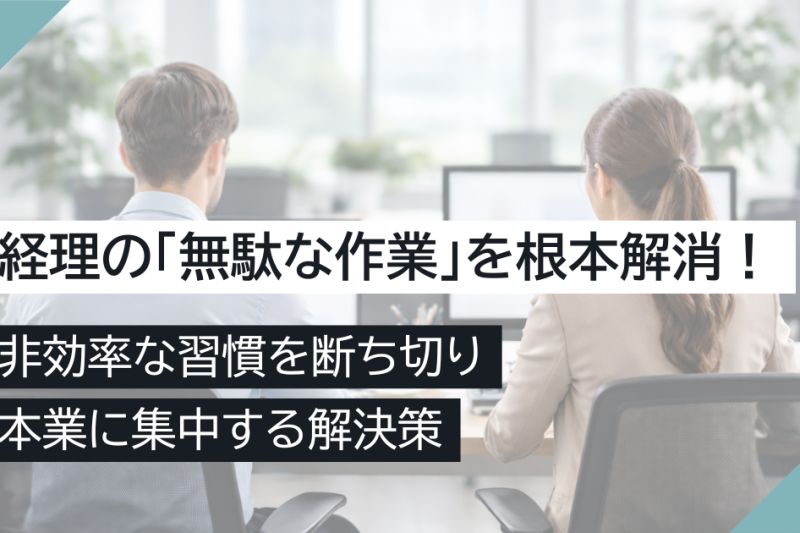会社設立の費用の勘定科目は?適切な仕訳方法を徹底解説
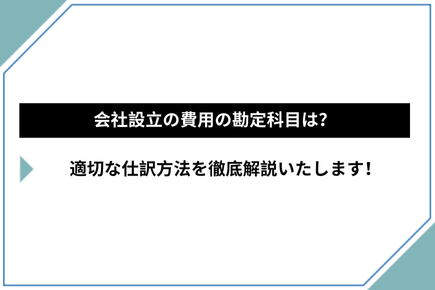
会社を設立するときは、定款を作成する際の手数料や、法人登記のための登録免許税など、さまざまな費用が発生します。
そしてこの費用の多さゆえに、「適切に仕訳が行えるだろうか」と不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、会社設立時にかかる費用の勘定科目や、実際の仕訳方法を解説します。
今後の起業に向けて「万全の準備を整えたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
会社設立費用の仕訳に必要な勘定科目

会社設立にかかった費用は、以下の2つの勘定科目を用いて仕訳を行います。
【会社設立費用の仕訳に必要な勘定科目】
- 創立費
- 開業費
会社を設立する際は、必要な準備や手続きに伴い、さまざまな費用が発生します。
発生した費用は、帳簿にきちんと記録しておかなければなりませんが、一つずつ勘定科目を細分化するとなると、膨大な労力を要してしまうでしょう。
そこで会社設立時の費用は、“設立前と設立後のどちらのタイミングで発生した費用なのか”という点を基準に振り分けます。
以下では、創立費と開業費のそれぞれに、どのような費用が含まれるのかを説明します。
なお、資本金は創立費・開業費のどちらにも該当しないので、別途計上が必要です。
創立費
創立費とは、会社設立の準備から実際に設立するまでにかかった費用のことです。
創立費に該当する具体的な項目は、以下の通りです。
【創立費に該当する費用の例】
- 定款作成のための収入印紙代や謄本代
- 発起人への報酬・使用人への給与
- 行政書士や司法書士への報酬
- 事務所の賃貸料
- 登録免許税
- 金融機関の取扱手数料
建設業や飲食業、人材派遣業といった、行政からの許認可が必要な業界で起業する場合は、それにかかる費用も創立費に含まれます。
ほかにも、会社設立に関するミーティングを喫茶店で行った場合、その際の飲食代や交通費も該当します。
開業費
会社設立後から営業を開始するまでの、開業準備にかかった費用を開業費といいます。
開業費の具体例は、以下の通りです。
【開業費に該当する費用の例】
- 営業開始に関わる研修費
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 名刺や印鑑の作成費
- ホームページの作成費
- オフィスの備品費
開業準備にかかるさまざまな費用を開業費として計上できますが、経常的な費用はこれに該当しません。
経常的な費用とは、事務所の水道光熱費や通信費、商品の仕入高など、開業後も継続的に発生する費用を指します。
会社設立時の払い込みに対応する勘定科目

会社を設立するときには、創立費や開業費とは別に、会社経営の元手となるお金も用意しなければなりません。
こうした会社設立時におけるお金の払い込みの仕訳では、以下の2つの勘定科目を使用します。
【会社設立時の払い込みに対応する勘定科目】
- 資本金
- 資本準備金
ここでは、この資本金と資本準備金について詳しく解説します。
資本金
資本金とは、会社が事業を行うために必要なお金のことです。
会社を設立するときは、設立の企画・出資・準備を行う“発起人”が、この資本金を個人口座に準備します。
資本金は法人用の口座で管理するものですが、会社設立前には銀行口座を開設できないため、一時的に個人口座に入金しておくのです。
法人用の口座を開設できたら、速やかに個人口座から法人口座に移し替える必要があります。
資本準備金
会社経営を行うために払い込んだ元手のうち、資本金として計上しなかった金額を資本準備金といいます。
経営の悪化や急な支出といった、万が一の事態に備えて準備しておく資金です。
資本準備金の限度額は、資本金として払い込んだ金額の2分の1までと定められています。
会社設立までに必要な費用

ここまでの内容で、会社設立時の仕訳に用いる4つの勘定科目について、ご理解いただけたのではないでしょうか。
以下ではそのうちの一つの勘定科目である、創立費に含まれる費用を細分化して解説します。
【会社設立までに必要な費用】
- 定款用の収入印紙代
- 定款の認証手数料
- 登録免許税
- 定款の謄本発行費
- 行政書士や司法書士への報酬
会社設立に欠かせない手続きや書類についても記載しておりますので、その点も押さえながらご覧ください。
定款用の収入印紙代
会社を設立するには、“定款”とよばれる、企業の根本原則が記載された書類を作成する必要があります。
そして、この定款を作成するために必要な費用の一つが、収入印紙代です。
定款には、電子定款と紙の定款の2種類がありますが、紙の定款を作成する場合は、40,000円の収入印紙代が発生します。
電子定款では、収入印紙代はかかりません。
参照元:日本公証人連合会
定款の認証手数料
定款を作成したあとは、その定款が正当なものであるということを、公証人に証明してもらう必要があります。
これが、“定款認証”とよばれる手続きです。
定款認証を受けられる場所は、会社の本店の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に所属する公証役場です。
そして、この認証を受ける際には、認証手数料が発生します。
認証手数料は、以下のように資本金の額に応じて変動します。
【定款の認証手数料】
| 資本金 | 手数料 |
| 1,000,000円未満 | 30,000円 |
| 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 40,000円 |
| 上記の金額以外 | 50,000円 |
なお定款認証は、株式会社および一般社団法人、一般財団法人を設立する際に必須です。
合同会社や合資会社、合名会社など、株式を発行しない持分会社においては、認証を受けなくても問題ありません。
参照元:日本公証人連合会
登録免許税
定款認証を終えたら、法務局にて“法人登記”を行います。
法人登記とは、定款で定めた称号や本店所在地、事業の目的などを法務局に登録して、一般に開示するための手続きです。
そして、この法人登記の手続きの際に納めなければならないのが、登録免許税です。
登録免許税の金額は、150,000円もしくは資本金の0.7%のいずれか高いほうと定められています。
そのため登録免許税は、最低でも150,000円はかかると覚えておきましょう。
参照元:日本公証人連合会
定款の謄本発行費
先述した法人登記を行う際の必要書類の一つに、定款の謄本があります。
定款の謄本は、公証役場にて発行してもらうことが可能ですので、定款認証のときに一緒に請求しておくとよいでしょう。
謄本の発行費は1枚につき250円です。
参照元:日本公証人連合会
行政書士や司法書士への報酬
ここまで説明した会社設立の手続きは、行政書士や司法書士に依頼することが可能です。
もちろん、ご自身で一から行うことも可能ですが、慣れない手続きや必要書類の準備で、思いのほか労力や時間を費やしてしまうかもしれません。
その場合は、こうした士業に依頼することで各手続きを円滑に進められます。
ただし依頼する際は、会社設立に必要な費用とは別に、行政書士や司法書士への報酬も用意しておく必要があります。
報酬の相場は、行政書士で75,000円程度、司法書士で100,000円程度です。
また各士業に依頼できる業務範囲については、以下の表をご覧ください。
【士業に依頼できる業務範囲】
| 職種 | 業務内容 |
| 行政書士 | 定款作成・認証(申請は不可)、許認可申請、社用車申請 |
| 司法書士 | 定款作成・認証、登記申請・変更手続き |
士業に依頼するときは、特定の業務のみを依頼する“スポット契約”と、一定期間継続してサポートしてもらえる“顧問契約”の2種類から選択できます。
契約方法によって報酬額が変動しますので、ご自身がサポートしてほしい範囲を、事前に決めておくことが大切です。
会社設立の流れに沿った費用の仕訳方法

会社を設立するまでに必要な費用について理解できたところで、ここからは、実際の仕訳方法を押さえていきましょう。
【会社設立の流れに沿った費用の仕訳方法】
- 資本金を払い込んだとき
- 会社設立の登録免許税を支払ったとき
- 開業準備のために市場調査費を支払ったとき
- 決算処理で繰延資産を償却したとき
以下では上記のパターンごとの仕訳方法を、資本金として5,000,000円を用意した場合を想定して説明していきます。
資本金を払い込んだとき
会社を設立するときは、最初に資本金の払い込みの仕訳から行います。
ただし、すでに記事内で説明した通り、法人口座は会社設立後でないと開設できないため、資本金は一時的に発起人の個人口座に保管しておく必要があります。
この点を考慮して、想定されるパターン別に資本金の仕訳方法を見ていきましょう。
まずは、発起人の個人口座に、資本金を預け入れた場合の仕訳方法です。
【資本金を発起人の個人口座に預け入れた際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 預け金 | 5,000,000円 | 資本金 | 5,000,000円 | 資本金の払い込み |
発起人の個人口座に預け入れた際は、会社名義の口座と区別するために“預け金”で処理します。
この預け金から、会社設立の準備にかかる費用4,000,000円を支払う場合の仕訳は、以下の通りです。
【発起人の個人口座にある資本金から創立費を支払った際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 創立費 | 4,000,000円 | 預け金 | 4,000,000円 | 創立費の支払い |
上記は、預け金から創立費を支払ったという旨の会計処理を表しています。
続いて、発起人の個人口座に残っている1,000,000円を、会社設立後の法人口座に移したときの仕訳方法を解説します。
【発起人の個人口座にある資本金を法人口座に移した際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 普通預金 | 1,000,000円 | 預け金 | 1,000,000円 | 普通預金に預け入れ |
こちらは、預け金に仕訳を行った資本金の残りを、法人口座に預け入れたという処理です。
なお例で使用した“預け金”は、“現金”や“仮払金”といった、ほかの科目で代用しても問題ありません。
会社設立の登録免許税を支払ったとき
資本金の仕訳を終えたら、次は会社設立の準備にかかった費用の仕訳を行いましょう。
ここでは、法人登記時の登録免許税を支払ったときを例に、仕訳方法を説明します。
登録免許税は会社設立の準備段階で発生した費用、つまり設立前に支払ったお金のため、使用する勘定科目は“創立費”です。
【登録免許税を支払った際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 創立費 | 150,000円 | 現金 | 150,000円 | 登録免許税 |
登録免許税は、150,000円もしくは資本金の0.7%のいずれか高いほうを支払います。
今回は資本金5,000,000円の想定で、5,000,000円×0.7%=35,000円となるため、前者の150,000円を適用します。
開業準備のために市場調査費を支払ったとき

会社設立後から開業までにかかった費用は、“開業費”として計上します。
開業準備のために支払った市場調査費は、以下のように仕訳を行います。
【市場調査費を支払った際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業費 | 500,000円 | 現金 | 500,000円 | 市場調査費 |
開業費は、上記のように明細書ごとに入力するのが望ましいですが、詳細な内訳を別途集計しているときは、まとめて入力しても問題ありません。
ただし、計上額の根拠となる明細書と、その金額に関する領収書はきちんと保管しておくことが求められます。
この場合の仕訳では、1行にまとめて入力して、摘要欄に“開業準備 別紙明細”と記載します。
決算処理で繰延資産を償却したとき
ここでは、営業開始から月日が経ち、決算の時期を迎えたときの仕訳方法を説明します。
会社設立のために支払った創立費や開業費は、その名前から経費と思われがちですが、実際には“繰延資産”という資産の科目に該当します。
繰延資産は、毎年少しずつ経費として割りあてることが可能です。
この少しずつ割りあてる処理を“償却”とよび、決算時に償却処理することで利益を圧縮できるため、節税効果を得られます。
繰延資産を償却処理する際の、仕訳方法は以下の通りです。
【創立費を償却した際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 創立費償却 | 30,000円 | 創立費 | 30,000円 | 償却額 |
【開業費を償却した際の仕訳】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 開業費償却 | 30,000円 | 開業費 | 30,000円 | 償却額 |
なお、会計上の償却期間は、創立費と開業費のどちらも5年間と定められていますので、この期間で均等に償却する必要があります。
お悩みはございませんか? この業務は依頼できるのかな?
といったご質問等まずはご相談ください。
日常業務から会計システム導入まであらゆる経理業務をサポートする
オンライン経理のCASTER BIZ accountingです!

- 「サービス資料」をご提供いたします
- 貴社の業種業界に合わせた「導入事例」をご紹介いたします
- ご希望で「オンライン面談」をご予約いただけます
- 現状の「課題整理」をお手伝いいたします
- 導入後の「ご活用イメージ」をご提案いたします
会社設立のために支払った費用は、創立費と開業費で仕訳を行う

今回は、会社設立にかかった費用の勘定科目や、具体的な仕訳方法を解説しました。
会社を設立する際は、定款の収入印紙代や認証手数料、また開業に向けての広告宣伝費や市場調査費など、さまざまな費用が発生します。
これらの費用を仕訳するときは、会社設立の前後どちらの出費なのかという点を基準に、創立費と開業費の2つの勘定科目を使い分けましょう。
また会社設立時の払い込みも、資本金と資本準備金の勘定科目を用いて適切に仕訳を行うことが大切です。
「適切な勘定科目や仕訳方法はわかったけれど、一人で行うのは不安……」という方は、ぜひオンライン経理のCASTER BIZ accountingにご相談ください。
実務経験豊富な経理のプロが、会社設立時の仕訳をサポートいたします。