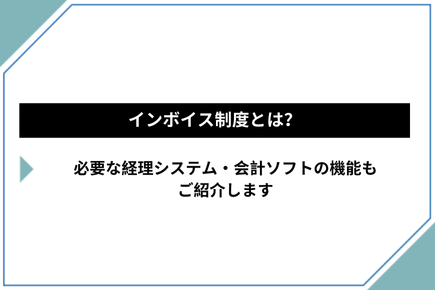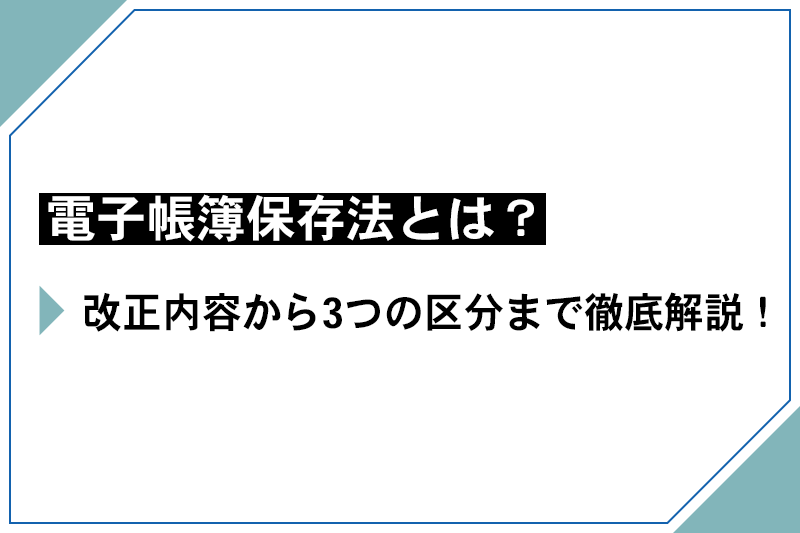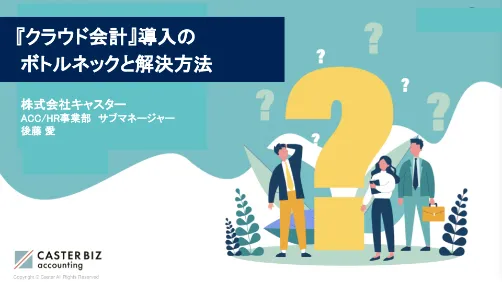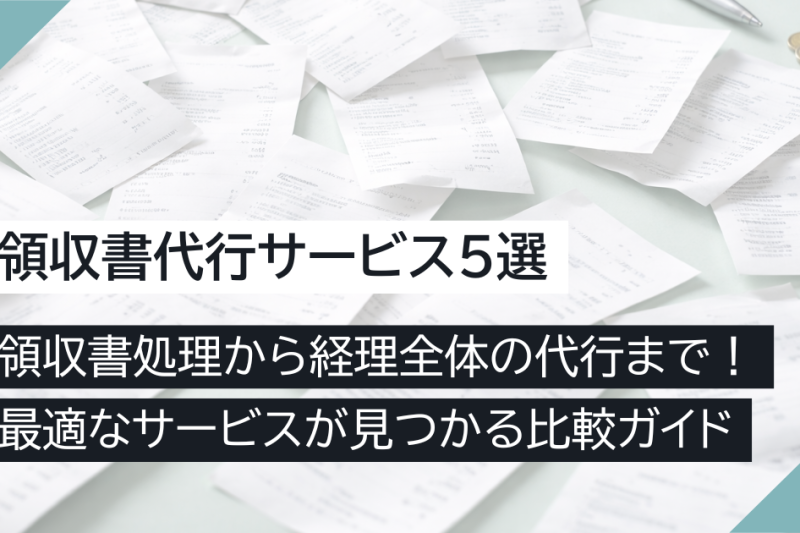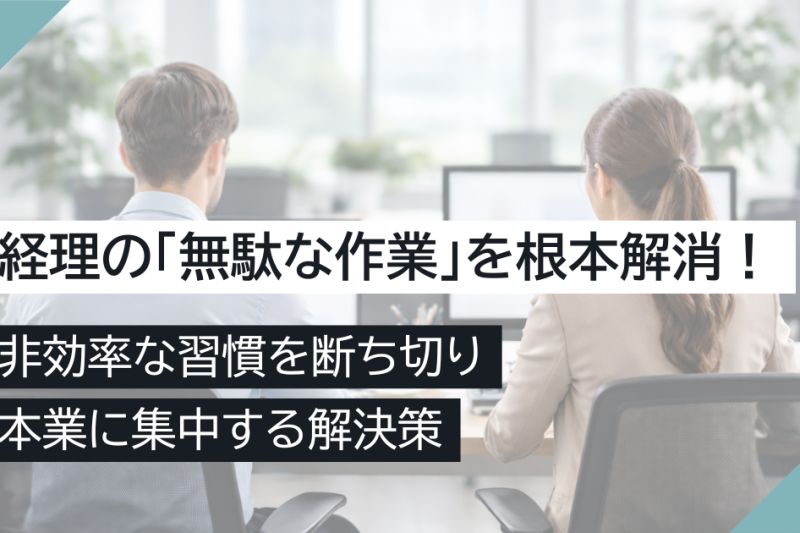インボイス制度の導入で経費精算と経費処理はどう変わる?
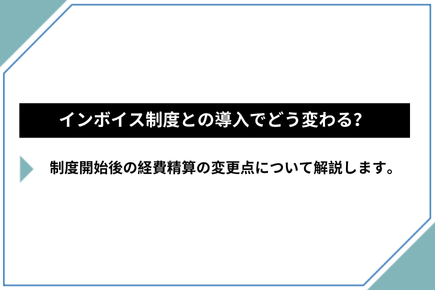
2023年10月から開始したインボイス制度によって、経費精算に付随する経費処理についても、ルールが変更されました。
適切な経費精算を遂行するためにも、変更された項目はきちんと理解しておきたいものです。
そこで本記事では、インボイス制度開始に伴う経費精算の変更点や、変更後の経費精算業務の流れを解説します。
インボイス制度を適用したあとの経理業務について、理解を深めたい事業者様は、ぜひご覧ください。
インボイス制度開始後の経費精算の変更点

インボイス制度が開始されたことで、経費精算処理には以下の変更が伴います。
【インボイス制度開始後の経費精算の変更点】
- 30,000円未満の経費・仕入れの領収書の取り扱い
- 領収書やレシートの種類ごとの仕分け
- 適格請求書および適格簡易請求書の記載項目
- 帳簿を作成する際のルール
それでは、具体的に紹介していきます。
30,000円未満の経費・仕入れの領収書の取り扱い
インボイス制度の導入によって、30,000円未満の領収書に認められていた特例が廃止されました。
もとは領収書がなくても、必要事項を帳簿に保存すれば仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度導入後は金額に関係なく、領収書類の保存が必須となったのです。
くわえて、その領収書やレシートは、適格請求書および適格簡易請求書の記載要件に一致したものでなければなりません。
なお、30,000円未満でも、以下の取引については請求書の発行が現状では困難なため、帳簿のみの保存であっても仕入税額控除が認められます。
30,000円未満の取引で、帳簿のみの保存が認められるもの
- 30,000円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 30,000円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入費
社内全体でインボイス制度導入後の変更点についての理解を深め、30,000円未満の領収書やレシートに対する適切な対応を求めましょう。
参照元:国税庁
領収書やレシートの種類ごとの仕分け
先述の通り、仕入税額控除には適格請求書と適格簡易請求書の記載要件に合致した領収書やレシートの保存が必要となり、その仕分けも欠かせません。
そこで以下の4つの分類に分けると、スムーズな経費精算が叶います。
経費精算を行う際の4つの分類
- 適格請求書と適格簡易請求書の記載要件を満たした領収書とレシート
- 免税事業者や適格請求書発行登録が済んでいない課税事業者が発行した領収書とレシート
- 帳簿への保存のみで、仕入税額控除が認められる経費
- 領収書やレシートがなく、仕入税額控除の対象ではない経費
ちなみに、免税事業者と適格請求書発行登録が済んでいない課税事業者は、仕入税額控除に必要な適格請求書が発行できない決まりとなっています。
これらの事業者から各請求書を受領しても、仕入税額控除の対象にはならないので留意してください。
適格請求書と適格簡易請求書の記載項目
インボイス制度による仕入税額控除を受けるには、先ほどの仕分けとあわせて、適格請求書と適格簡易請求書の記載項目に漏れがないかどうかの確認も必要です。
以下に、それぞれの記載するべき項目をまとめたので、記載漏れをチェックする際の参考にしてみてください。
適格請求書および適格簡易請求書の記載項目
|
|
記載項目 |
|
適格請求書 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
取引年月日 取引内容 ※軽減税率の対象品目である旨税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 税率ごとに区分した消費税額 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
|
適格簡易請求書 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
取引年月日 取引内容 ※軽減税率の対象品目である旨 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込) 税率ごとに区分した消費税額または適用税率 |
上記の表から、適格簡易請求書は適格請求書よりも、記載項目が簡略化されていることが読み取れます。
なお、領収書やレシートの発行元が適格請求書発行事業者であっても、内容の誤りや記載項目に不備があると、仕入税額控除は受けられません。
そういったケースを避けるために、領収書やレシートを受領する際は不備がないかどうか、そのときにきちんと確認しましょう。
参照元:国税庁
帳簿を作成する際のルール
インボイス制度の開始に伴って、経理業務の担当者には、適格請求書や適格簡易請求書に関する記帳への対応が求められるようになりました。
仕入税額控除を受けるために、以下の4つの項目を帳簿に記帳します。
仕入税額控除を受ける際の帳簿への記帳項目
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容と税率(軽減税率の対象品目である旨)
- 課税仕入れに係る支払対価の額
消費税の記帳には、“税込経理方式”と“税抜経理方式”の2種類が存在します。
どちらを選んでも問題ありませんが、記帳する際はすべての取引で、同じ方式に統一しなければなりません。
関連記事:インボイス制度に必要な経理システム・会計ソフトの機能とは
参照:国税庁
インボイス制度下の経費精算の流れ

ここまでの内容を受けて、インボイス制度が導入されたあとの経費精算の変更点は、把握できたのではないでしょうか。
ここからは、インボイス制度導入後の、経費精算の大まかな流れをお伝えします。
【インボイス制度下の経費精算の流れ】
- 領収書やレシートが適格請求書や適格簡易請求書の対象かどうかを判断する
- 項目の記載漏れがないか確認する
以下で、詳しく解説します。
領収書やレシートが適格請求書や適格簡易請求書の対象かどうかを判断する
まずは、適格請求書や適格簡易請求書に該当する領収書やレシートなのかという点を判断します。
繰り返しになりますが、各請求書は適格請求書発行事業者として登録されている事業者しか発行することができません。
つまり、登録していない事業者が発行した領収書やレシートは、適格請求書や適格簡易請求書として認められないので、必ず確認してください。
項目の記載漏れがないか確認する
適格請求書や適格簡易請求書に該当する領収書やレシートが、それぞれの記載要件を満たしているかどうかも確認します。
記載要件を確認する場合は、以下の項目を参考にしてみてください。
適格請求書と適格簡易請求書に必ず記載しなければならない項目
|
|
適格請求書 |
適格簡易請求書 |
|
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
〇 |
〇 |
|
取引年月日 |
〇 |
〇 |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
〇 |
〇 |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
〇 |
〇 ※適用税率の記載は、不要 |
|
税率ごとに区分した消費税額 |
〇 |
〇 ※消費税額は、適用税率に変更しても構わない |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
〇 |
× |
それぞれの記載要件が満たされていないと、仕入税額控除の対象外となるため、必ず確認しましょう。
適格請求書および適格簡易請求書の保存期間
適格請求書と適格簡易請求書は、発行元や受領側にかかわらず、一定期間保存する義務があります。
保存期間は、各請求書を発行した日が属する事業年度の最終日の翌日から、2ヶ月が経過した日を起点に7年間です。
以下のケースを例に、具体的な保存期間を記載しました。
2024年2月17日に、適格請求書または適格簡易請求書を発行した場合の保存期間
- 事業年度の最終日:2024年12月31日
- 事業年度の最終日の翌日:2025年1月1日
- 2ヶ月が経過した日:2025年3月1日
- 保存期間:2025年3月1日から7年間
なお、レシートは感熱紙で発行されているため、紙のまま長期間保管すると、印刷された文字が消えてしまう可能性があります。
したがって、万が一文字が消えてしまっても確認できるよう、事前にスキャンあるいは撮影といった方法をとっておくと安心です。
参照元:国税庁
お悩みはございませんか? この業務は依頼できるのかな?
といったご質問等まずはご相談ください。
日常業務から会計システム導入まであらゆる経理業務をサポートする
オンライン経理のCASTER BIZ accountingです!

- 「サービス資料」をご提供いたします
- 貴社の業種業界に合わせた「導入事例」をご紹介いたします
- ご希望で「オンライン面談」をご予約いただけます
- 現状の「課題整理」をお手伝いいたします
- 導入後の「ご活用イメージ」をご提案いたします
仕入税額控除を受けられる経費

経費精算を行う際、仕入税額控除が受けられる経費は一般的に、それぞれの記載要件を満たしているかどうかで判断します。
そこで以下では、適格請求書と適格簡易請求書の2つに分けて解説します。
【仕入税額控除が受けられる経費】
- 適格請求書がなくても仕入税額控除が可能な経費
- 適格簡易請求書で仕入税額控除が可能な経費
それでは順に、詳細を確認していきましょう。
適格請求書がなくても仕入税額控除が可能な経費
帳簿に記帳されていれば、適格請求書がなくとも以下の項目の費用は、仕入税額控除が認められます。
帳簿のみの記帳で、仕入税額控除が認められる項目
- 30,000円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 取引年月日を除いた入場券のうち、使用の際に回収されるもの
- 適格請求書発行事業者ではない者からの古物の購入費
- 適格請求書発行事業者ではない質屋からの質物の取得費
- 適格請求書発行事業者ではない宅地建物取引業者からの建物の購入費
- 適格請求書発行事業者ではない者からの再生資源および再生部品の購入費
- 30,000円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入費
- 郵便ポストに投函した郵便や貨物サービス
- 従業員に支給する出張旅費や宿泊費、日当および通勤手当
なお、上記のなかには、上限金額や適用要件があらかじめ設定されているものがあるので、事前に国税庁のホームページを確認しましょう。
参照元:国税庁
適格簡易請求書で仕入税額控除が可能な経費
適格簡易請求書は、“不特定多数の者に対して販売を行う事業者”のみが発行でき、さらに記載要件を満たしたものだけが仕入税額控除を受けることが可能です。
適格簡易請求書を発行できる事業者は、以下が該当します。
適格簡易請求書を発行できる事業者
- 小売業者
- 飲食店業者
- 写真業者
- 旅行業者
- タクシー業者
- 駐車場業者
- その他、これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の方に資産の譲渡を行う事業
不特定かつ多数の方に資産の譲渡を行う事業には、ホテルや旅館などの宿泊サービスや航空サービス、レンタカー事業などが含まれます。
受領したレシートが仕入税額控除の対象かどうかを確認するのは、経理担当者にとって非常に手間のかかる作業の一つです。
そのような場合でも、自動で登録番号を記録できる経費精算システムを導入すると、経理担当者の負担を減らせます。
インボイス制度の導入後の経費精算で気をつけるべき点

インボイス制度の導入後、従業員が領収書を受領する際は、宛名を法人名にすることが求められます。
宛名が従業員の個人名だった場合、企業の支出ではないと判断されて、仕入税額控除が認められない可能性があるためです。
もし、個人名で領収書を受領していた場合は、立替金精算書の作成や保存による証明が必要です。
その際、立替金精算書は領収書を受領した従業員に作成してもらい、企業の経費の立替であることを明らかにする必要もあります。
適格請求書と立替金精算書は、あわせて保存しなければ企業の支出と判断されないため、その点は留意してください。
免税事業者と取引する場合の経費精算について
ここからは、免税事業者と取引する際の経費精算で、気をつけておきたい点を紹介します。
【免税事業者と取引する場合の経費精算について】
- 免税事業者は適格請求書と適格簡易請求書を発行できない
- 2029年9月までは50~80%の仕入税額控除ができる
これらの点を事前に理解しておき、免税事業者との取引をスムーズに行いましょう。
免税事業者は適格請求書と適格簡易請求書を発行できない
免税事業者は、適格請求書発行事業者に該当しないため、適格請求書ならびに適格簡易請求書を発行することができません。
したがって、免税事業者と取引を行う場合は、仕入税額控除が受けられないことを頭に入れておきましょう。
2029年9月までは50~80%の仕入税額控除ができる
免税事業者との取引においては、仕入税額控除が認められないと前述しました。
しかし2029年9月までは、一定の仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
その経過措置の適用期間と控除の割合については、以下の通りです。
経過措置の適用期間と控除の割合
- 2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除
- 2026年10月1日~2029年9月30日:50%控除
このように2029年9月30日までは、免税事業者との取引であっても、50~80%の仕入税額控除が受けられます。
経理のお困りごとはCASTER BIZ accountingにお任せください

インボイス制度への対応のほかにも、月次処理やレポート作成などの経理業務に負担を感じていませんか?
そのような負担を減らしたい場合は、株式会社キャスターが展開しているオンライン経理のCASTER BIZ accountingの活用がおすすめです。
CASTER BIZ accountingには、経理の実務経験3年以上のスタッフが多数在籍しており、帳簿への記帳や月次決算などの業務を幅広く対応いたします。
したがって、自社の経理担当者は、コア業務に専念することが可能です。
また、経理業務を部分的に担当するCASTER BIZ accounting BPOと、月次業務を行う
CASTER BIZ accountingに分かれており、ぴったりのプランをお選びいただけます。
貴社が抱えている経理業務のお悩みを無料でお伺いし、最適なプランをご提案させていただくので、お気軽にお問い合わせください。
インボイス制度導入後の経費精算や経費処理では、領収書やレシートの取り扱い方が変わる
今回は、インボイス制度が導入されたあとの領収書やレシートの取り扱い方や、経費精算の変更点を解説しました。
インボイス制度下では、30,000円未満の領収書やレシートも、受領と保存が必須となります。
その場合は、適格請求書や適格簡易請求書の記載要件が揃ったものでなければなりません。
なお、インボイス制度への対応が伴う経理業務の負担を軽減させたいのであれば、業務委託するのも一つの方法です。
経理アウトソーシングサービスのCASTER BIZ accountingでは、実務経験豊富なスタッフが、インボイス制度に遵守した業務をサポートしております。
「経理担当者の負担を減らしたい」とお考えの事業者様は、ぜひお問い合わせください。