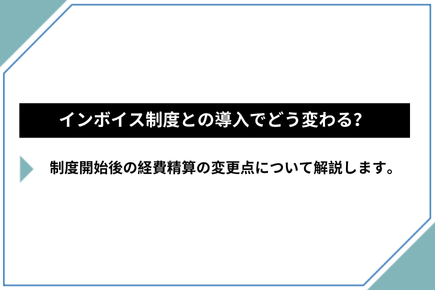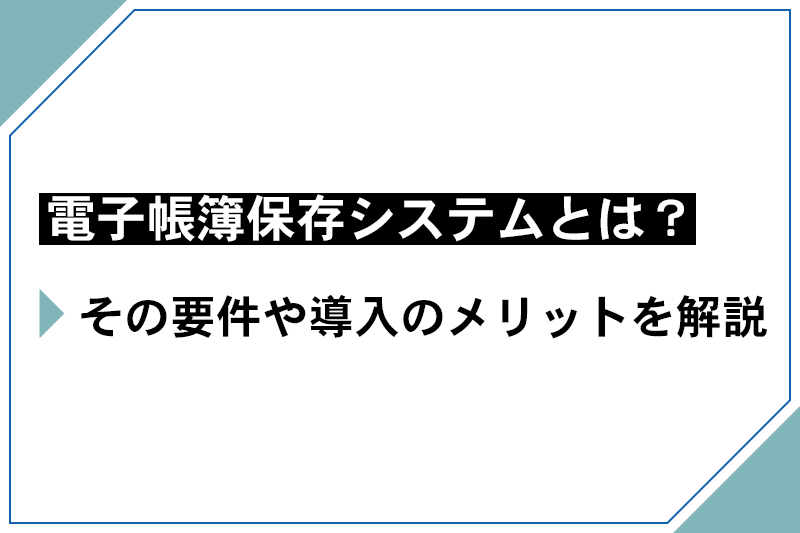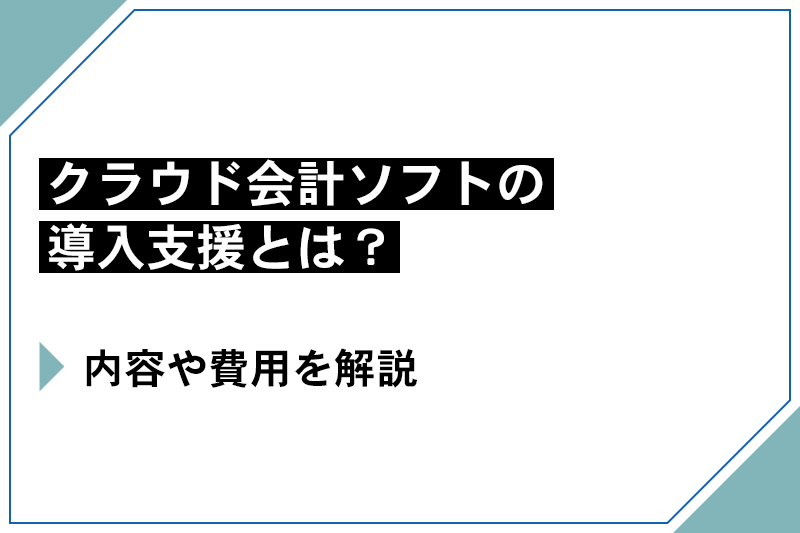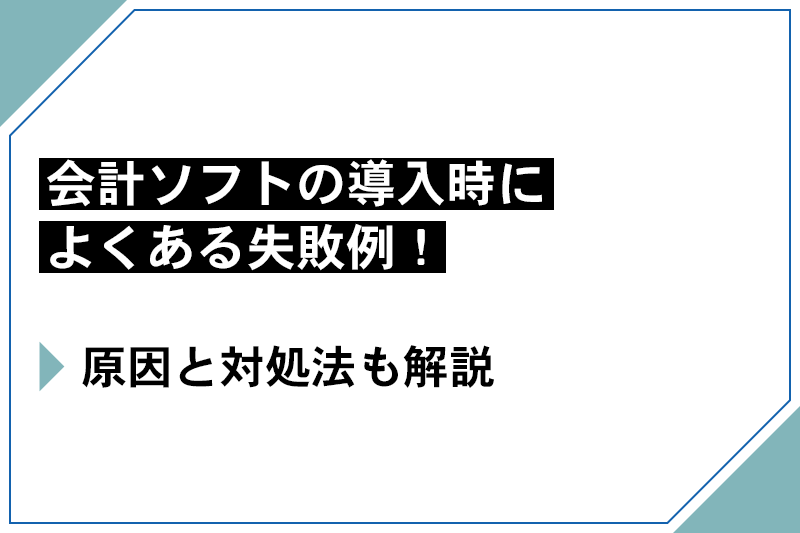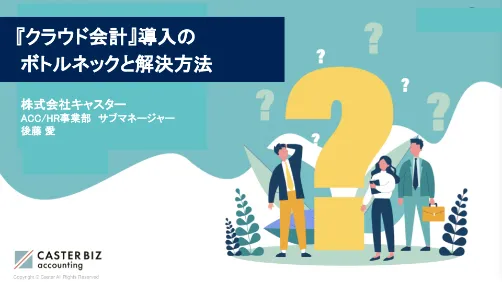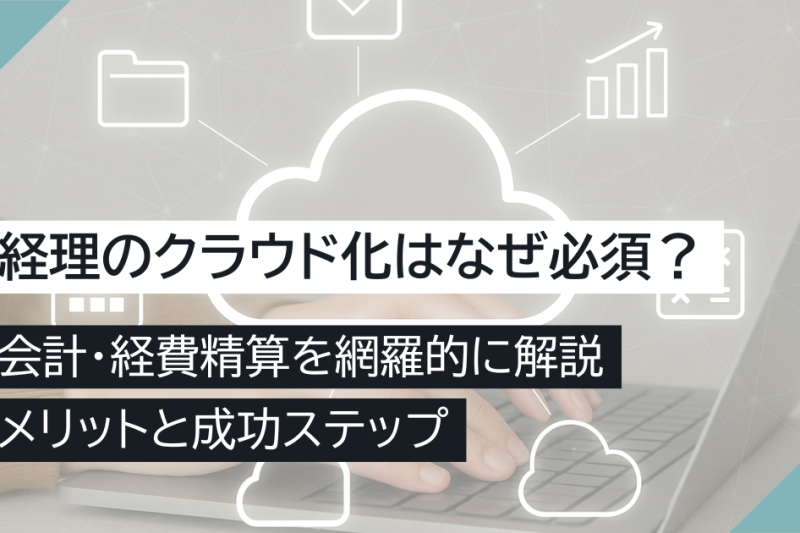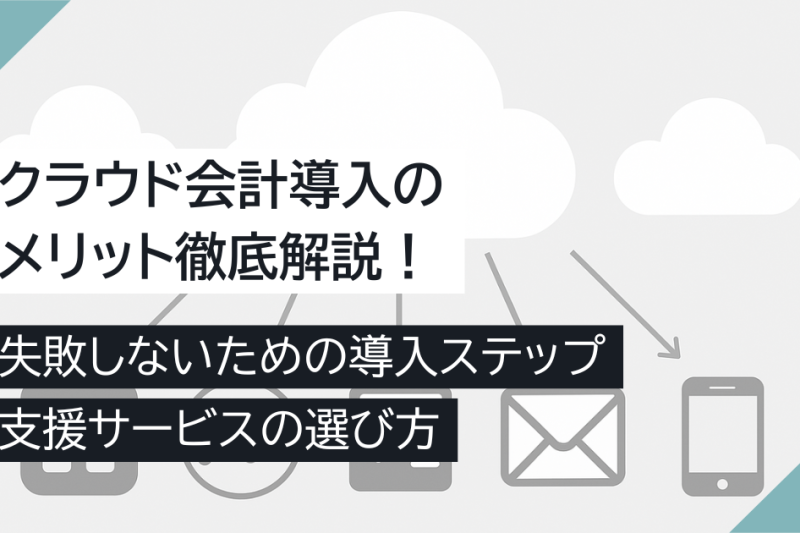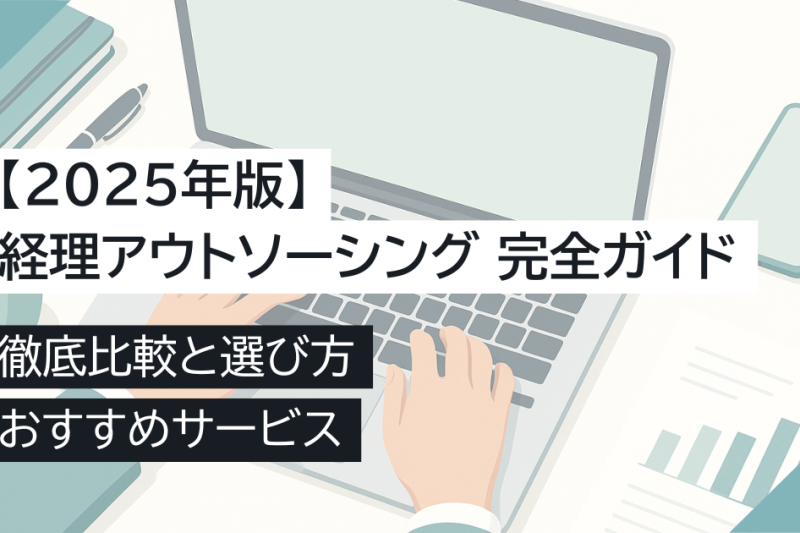インボイス制度に必要な経理システム・会計ソフトの機能とは
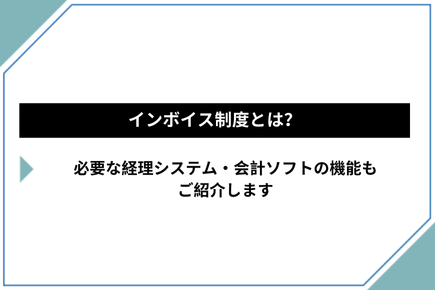
2023年にインボイス制度が施行されて以降、消費税額の計算が複雑化しています。
適正な消費税額の計算と仕入税額控除の申請には、インボイス制度に対応した経理システムや会計ソフトの活用が欠かせません。
そこで本記事では、インボイス制度の詳細をお伝えしたうえで、この制度に対応するための経理システム・会計ソフトに必要な機能を紹介します。
インボイス制度に適切に対応したい経理のご担当者様は、ぜひご一読ください。
インボイス制度とは

そもそもインボイス制度とは何かというと、事業者が複数の税率に対応して、消費税を正確に納めるための制度のことです。
事業者が納付する消費税額は、“売上時に受け取った消費税額-仕入れや経費で支払った消費税額”で算出します。
この仕組みを“仕入税額控除”といい、インボイス制度の施行後は、取引先から“適格請求書(=インボイス)”の発行を受けた場合に限り控除の対象と認められることとなりました。
この適格請求書がないと、納税する消費税額が正しいものであることを確認できません。
そのため、受け取った請求書だけではなく、自社が発行した請求書の写しも適切に保存しておきましょう。
なお、適格請求書の発行に際しては、税務署の審査を受けて、適格請求書発行事業者として認められる必要があります。
適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者のみと定められており、免税事業者の場合は適格請求書を発行できません。
では適格請求書と従来の請求書には、どのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、これらの違いにくわえて、インボイス制度導入から6年間にわたって設けられている経過措置や特例制度についても深掘りしていきます。
区分記載請求書と適格請求書との違い
従来の区分記載請求書から適格請求書に移行したことで大きく変わったのは、記載する項目が追加された点です。
区分記載請求書では、取引年月日や取引内容、軽減税率(8%)と標準税率(10%)を区別して記載する必要がありました。
適格請求書では、さらに記載項目が増えています。
具体的には、以下の項目を記載していないと適格請求書として認められません。
適格請求書に必須な記載項目
- 適格請求書発行事業者の名称または氏名と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 適格請求書を受け取る事業者の名称
インボイス制度が施行されてからは、“発行事業者の登録番号”・“適用税率”・“税率ごとの消費税率”の3つの記載項目が追加されました。
これは適格請求書発行事業者として登録されているかどうか、どの取引がどの税率に該当するのかといった点にくわえて、税率ごとの消費税額を明らかにするためです。
経過措置や特例制度
インボイス制度の開始を受けて、免税事業者との取引が続いている事業者の負担を減らすため、8割控除”とよばれる経過措置や“少額特例”といった特例制度が設けられています。
免税事業者はインボイスを発行できないと先述しましたが、これはつまり、事業者が課税仕入れで支払った消費税額は仕入税額控除の対象外になるということです。
このような事業者の負担を軽減するために、インボイス制度が施行された2023年10月以降、6年間にわたって徐々に控除額を減らしていく経過措置がとられているのです。
これを8割控除といい、2026年までの3年間は仕入税額の80%を、その後2029年までの3年間は50%が控除されます。
また、基準期間における課税売上高が1億円以下といった、一定の要件を満たす事業者の場合、課税仕入れ額が税込み10,000円以下であれば仕入税額控除が可能です。
これは少額特例とよばれ、インボイスがなくても帳簿を保存していれば控除を受けられます。
なお、少額特例の適用期間も、8割控除と同様に2029年9月30日までとなります。
インボイス制度への対応が必要なシステムの範囲

インボイス制度によって生じる複雑な要件に対応するためには、経理システムや会計ソフトをはじめとした各種システムの整備が欠かせません。
とはいえ、既存のシステムの改修には相応の時間を要するため、早めの対応が求められます。
また、これまで経理システムや会計ソフトを活用していなかった場合は、新たに導入を検討する必要があるでしょう。
インボイス制度に不備なく対応するにあたって、影響を受けるシステムの範囲は以下の通りです。
インボイス制度への対応が必要なシステムの例
| システム | 必要事項 |
| 請求書発行システム | 適格請求書の発行に必要な項目をすべて記載できる |
| 会計ソフト | 免税事業者からの仕入れに関する税区分を追加できる
適格請求書とそうでないものを区分・管理できる |
| 販売管理・受発注システム | 取引先ごとに課税事業者、免税事業者を識別できる |
| POSシステム | 複数税率に対応できる |
上記の表のうち、経理システムの一種である請求書発行システムには、適格請求書に必要な記載事項に対応していることが求められます。
また会計ソフトは、適格請求書とそれ以外の請求書を区分・管理できるかどうかが重要なポイントです。
IT導入補助金について
自社のシステムを新たに構築しなおすには、それなりの費用がかかるため、なかなか実行できない企業もあるかもしれません。
しかし、中小企業や小規模事業者であれば、IT導入補助金の“インボイス枠”を利用することで、インボイスに対応したシステムの導入費用を補填できます。
会計・受発注・決済などの機能を有したソフトウェアのほか、パソコンやタブレットといったハードウェアの導入費用に充てるとよいでしょう。
インボイス枠の場合、中小企業であれば導入費用の3/4以内を、小規模事業者の場合は4/5以内が補助されるため、ぜひ活用したいところです。
インボイス制度と会計ソフトの関係性

項では、インボイス制度への対応が必要になる経理システムや会計ソフトの機能について解説しました。
インボイス制度においては、双方が適切に対応できていることを前提としたうえで、経理システム以上に会計ソフトに比重を置く必要があります。
経理システムでは、適格請求書の発行・管理業務の効率化が主となります。
会計ソフトは、インボイス制度の重要な部分である消費税額の区別や計算、帳簿の作成などを正しく行うため、非常に重要です。
ここからは、そんな会計ソフトに焦点を当てて、インボイス制度との関係性を見ていきましょう。
正確な消費税区分が必要
消費税の計算には複数の税率を正確に区分しなければならず、複雑な作業を伴うためミスが発生しやすくなっています。
そのミスを軽減するためには、会計ソフトに入力した仕分けと連動して申告書を作成したり、納税額を計算したりできることが非常に重要です。
インボイス制度に準拠した消費税額の計算や、特例制度への対応を踏まえると、これらを正確かつ効率的に進められる会計ソフトが不可欠なのです。
特例制度のための帳簿作成が必要
先述のようなインボイス制度の経過措置や特例制度を受けるためには、適切な帳簿の作成が必要です。
たとえば、8割控除を受ける際には、その適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿に記載することが要件とされています。
少額特例の場合は、取引先の名称や取引年月日、取引内容、課税仕入れに係る支払対価の額などの記載が求められます。
どちらも記載漏れのような不備があると、経過措置や特例制度を受けられない可能性があるのです。
このような特例制度を漏れなく受けるためにも、インボイス制度に対応した帳簿を作成できる会計ソフトが必要です。
インボイス制度への対応で押さえておきたい会計ソフトの機能

インボイス制度と会計ソフトには、正確な消費税率の計算や、帳簿の作成などを適切に実行するうえで深い関係があることがわかりました。
ここからは、インボイス制度への対応にあたって押さえておきたい会計ソフトの機能を紹介します。
【インボイス制度への対応に必須の会計ソフトの機能】
- 適格請求書とそれ以外の請求書の区分・管理機能
- 改正電子帳簿保存法に対応できる機能
詳細は、以下をご確認ください。
適格請求書とそれ以外の請求書の区分・管理機能
仕入税額控除が適用されるのは、適格請求書発行事業者からの課税仕入れのみなので、会計ソフトには適格請求書とそれ以外の請求書を区分できる機能が求められます。
多くの取引先を抱えている事業者であればなおのこと、請求書を正確に区分する機能を有した会計ソフトを活用すれば、業務の負担が大幅に軽減できるでしょう。
また、特例制度にも対応できる会計ソフトであれば、煩雑な業務をシステムに任せられるので、さらに業務効率の向上が見込めます。
改正電子帳簿保存法に対応できる機能
インボイス制度に準じるためには、会計ソフトに“改正電子帳簿保存法”への対応が可能な機能が備わっていることを確認しましょう。
2024年1月に電子帳簿保存法が改正されて以降、データでやり取りする適格請求書である“電子インボイス”の保存が完全義務化されました。
電子インボイスを保存する際には、“真実性の確保”と“可視性の確保”といった2つの要件が設けられています。
具体的には、タイムスタンプを付したあとの授受、訂正や削除を確認できるシステム、検索機能の確保などが挙げられます。
会計ソフトには、この法律に抵触せずに電子インボイスを保存できる機能が求められるわけです。
自社においても、今後は適格請求書を電子データでやり取りするケースもあるでしょう。
そのような場合を想定して、改正電子帳簿保存法に対応可能な会計ソフトを導入することが重要です。
参照元:e-Gov法令検索 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
お悩みはございませんか? この業務は依頼できるのかな?
といったご質問等まずはご相談ください。
日常業務から会計システム導入まであらゆる経理業務をサポートする
オンライン経理のCASTER BIZ accountingです!

- 「サービス資料」をご提供いたします
- 貴社の業種業界に合わせた「導入事例」をご紹介いたします
- ご希望で「オンライン面談」をご予約いただけます
- 現状の「課題整理」をお手伝いいたします
- 導入後の「ご活用イメージ」をご提案いたします
インボイス制度に対応可能な会計ソフトを選ぶ際のポイント

インボイス制度に準拠するためには、適格請求書とそれ以外のものを区分する機能や、改正電子帳簿保存法への対応の可否が必要であることがおわかりいただけたでしょうか。
これらを押さえたうえで、会計ソフトを選ぶ際には以下の3つのポイントを確認してください。
【インボイス制度に対応可能な会計ソフトを選ぶ際のポイント】
- インボイス対応の自動仕訳機能がある
- 取引先ごとにインボイス登録の有無を管理できる
- 適正な消費税申告と税額計算機能がある
では、一つひとつ見ていきましょう。
ポイント①インボイス対応の自動仕訳機能がある
複雑な作業を伴うインボイス制度に対応するためには、請求書や領収書のデータをもとに、消費税額を自動で仕訳できる機能をもった会計ソフトを選ぶのがおすすめです。
インボイス制度においては、受領する請求書や領収書が制度の対象となるのかどうかを明確に分類する必要があり、そのうえで仕訳の消費税区分を分けることとなります。
消費税区分を自動化できれば、経理担当者の手間と時間を節約できるだけではなく、ミスが発生するリスクも抑えられます。
適格請求書を区分する機能のほか、消費税額の仕訳まで実行できる会計ソフトを導入することで、インボイス制度に関わる煩雑な業務をより効率化できるはずです。
ポイント②取引先ごとにインボイス登録の有無を管理できる
適格請求書発行事業者の登録の有無を、取引先ごとに分けて管理できる機能を備えた会計ソフトを選べば、インボイスに関わる業務効率を上げられます。
インボイス制度への対応にあたっては、請求書に記載されている登録番号を、国税庁の“適格請求書発行事業者公表サイト”で照会する必要があります。
これにより、取引先が適格請求書発行事業者であるか否かを確認するわけです。
しかし、このような作業を一つひとつこなすとなると多くの手間と時間がかかります。
取引先情報の管理ができる会計ソフトなら、取引先ごとにインボイス登録の有無を設定することが可能です。
そうすれば、適切な消費税区分が自動で反映されます。
仕訳のたびに消費税区分を確認して手入力する手間が省けるので、経理担当者の業務負担を大幅に軽減できるでしょう。
ポイント③適正な消費税申告と税額計算機能がある
複雑なインボイス制度に正確に対応するためには、消費税の申告書の作成や、消費税額の計算を実行する機能が整備されている会計ソフトを選ぶのがポイントです。
ただでさえ煩雑なインボイス制度ですが、そこに経過措置や特例制度が加わると、さらに手間がかかることになります。
そのため会計ソフトを選ぶ際は、適正な消費税申告書を作成するサポート機能や、消費税額を正確に計算できる機能を有しているかどうかが重要です。
インボイス制度に対応可能な経理システム・会計ソフトを導入しよう!

今回は、インボイス制度の詳細をお伝えしたうえで、その対応に不可欠な経理システム・会計ソフトの機能を解説しました。
インボイス制度が施行されて以降、経理システム・会計ソフトには制度に対応できる機能が求められています。
請求書を区分する機能や、改正電子帳簿保存法に準拠した機能などが搭載された会計ソフトを活用して、適正な消費税額の計算と仕入税額控除の申請に役立てましょう。
インボイス制度への対応にお困りであれば、業務委託サービスを利用するのも一案です。
経理の業務委託を請け負っているオンライン経理のCASTER BIZ accountingでは、インボイス制度に対応している会計システム導入のご支援をしおりますので、ぜひ一度お問い合わせください。